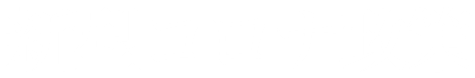質問主意書
厚生労働大臣は令和七年一月二十四日付けで、国立大学法人長崎大学を特定一種病原体等所持者として、また、同大学内の高度感染症研究センター実験棟を特定一種病原体等所持施設(以下、「BSL-4施設」という。)として指定した。
右について、昨年十一月十五日から一か月間パブリックコメントを実施した結果、九万二千三百六件の意見が寄せられており、その内容は、「わざわざ日本で研究する意味がわかりません」「長崎大学は活断層の上にあるようで、予期しない災害を非常に心配しています」「ほとんどの国民が知らないうちにこっそり改正するのは良くないです。もっと新聞やテレビで報道して意見を広く求めるべきです」「研究施設から外部に出て感染症が広がった場合の補償はありますか」など、施設の必要性への疑問や事故や災害への懸念が多数挙げられている。
国は、この施設において特定一種病原体を対象とした基礎研究や人材育成、特に疫学研究、感染機構研究、病態研究、医療応用研究などを行うとしているが、具体的な成果や便益のイメージが想起しづらい一方で、リスクの告知や対応、補償などの体制や経済的バックアップが不明確であるため、国の安全管理に対する具体的な取組や責任体制が問われていると考える。
以上を踏まえ、質問する。
吉川里奈(参政党)
人為的事故や災害の場合の備えについて
1 BSL-4施設では極めて危険な病原体が取り扱われることから、人為的事故や自然災害が発生した際の緊急対応は極めて重要であると考える。警察や消防はこの種の特定一種病原体に対応するための訓練を受け、必要な人材を確保しているのか、政府の把握するところを回答されたい。
2 事態が拡大した場合に自衛隊の出動や住民の避難が必要となる事態も想定されるが、そのような状況に対して具体的な計画が存在するのか、政府の把握するところを回答されたい。
3 近隣住民が避難や感染等の被害に遭った場合の補償について特別な法律を設ける必要性について、政府はどのように考えるか。
政府
1について
御指摘の「BSL-4施設」において「人為的事故や自然災害」が発生した場合も含め、「特定病原体等に係る事故・災害時対応指針」(令和五年九月厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課公表。以下「事故・災害時対応指針」という。)において、お尋ねの「警察」については、例えば、「事故・災害時の人命救助、立入禁止措置、交通規制」等を行うこととし、「消防」については、例えば、「事故・災害時の人命救助、消火、延焼防止」等を行うこととしているところ、これらを的確に行うため、必要な訓練を実施し、及び体制を確保しているところである。
2について
御指摘の「事態が拡大した場合」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「自衛隊の出動」については、個別の状況に応じ、関係法令等に従い、適切に対応することとなり、また、御指摘の「住民の避難」については、事故・災害時対応指針は、「特定病原体等について盗取、所在不明その他の事故が生じた場合、及び地震、火災その他の災害・・・が起こったことにより、当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合の事業者が整備しておくべき緊急連絡体制及び事業者が講じるべき応急措置その他必要な措置に関して、・・・関係機関における連絡体制、連携等に関する内部規定を策定するための指針となるものである」ところ、「特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、特定病原体等取扱施設の内部にいる者、病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告する」、「必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、ロープを張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努める」等としているところである。
3について
御指摘の「近隣住民」の「避難」については、一の2についてで述べたような「避難」を想定しており、また、御指摘の「近隣住民」の「感染等の被害に遭った場合の補償」については、個別の状況に応じ、民法(明治二十九年法律第八十九号)や国家賠償法(昭和二十二年法律第百二十五号)等に基づき対応が行われるものと考えており、新たに「補償について特別な法律を設ける」ことは現時点で検討していない。
吉川里奈(参政党)
地震に対する安全性について
BSL-4施設の「地震に対する安全性の確保」の基準は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(一種病原体等取扱施設の基準)第三十一条の二十七第三号によって建設省告示を引用している。しかし、同告示が地震リスクを含む立地条件を十分に考慮しておらず、致死率の高い特定一種病原体を取り扱う施設の場合の安全基準として不十分であると懸念している。そこで、地震発生時の対策と施設の安全性に関して、現在の基準の適切性と省令改正の必要性について、政府の見解を求めたい。
政府
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「地震発生時の対策と施設の安全性」の確保については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)第三十一条の二十七第三号の規定において、「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)に従い、又は当該基準の例により、地震に対する安全性の確保が図られていること」等とされ、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準(平成六年建設省告示第二千三百七十九号)において、「構造体の耐震性能」等について勘案すべき具体的な基準が示されているところ、当該基準を満たすことで、地震に対する安全性の確保が図られるものと考えており、御指摘の「省令改正」は現時点で検討していない。
吉川里奈(参政党)
成果の盗用や海外移転を防止する制度について
1 国内で行われる高リスク研究の成果が不正に流出することは、国家の安全保障上、看過できない問題であると考える。研究成果の国内外への流出を防ぐために、政府はどのような対策を講じているのか。
2 研究者や従事者に対するセキュリティ対策の強化は予定されているのか。
政府
お尋ねの「研究成果の国内外への流出を防ぐために、政府はどのような対策を講じているのか」については、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)、サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)等に基づき適切な対応を行うこととしている。
また、お尋ねの「セキュリティ対策の強化」については、例えば、令和六年度補正予算において、内閣府では、国内の研究機関等を対象に、国内外における共同研究等の実施に当たり、共同研究契約等の相手方等に関する情報の収集及び分析のために必要な経費を支援する「研究セキュリティ・インテグリティに関するリスクマネジメント体制整備支援事業」を行うこととしている。
吉川里奈(参政党)
研究の倫理基準について
1 特定一種病原体を用いた研究に関し、動物実験や人間での実験も含めた倫理基準につき、いかなる基準が適用されるか。
2 政府は、現在の倫理基準が十分であると考えているのか。また、これらの基準の見直しを行う予定はあるのか。
政府
お尋ねの「倫理基準」及び「いかなる基準が適用されるか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、国立感染症研究所及び国立大学法人長崎大学における御指摘の「特定一種病原体を用いた研究に関し」、御指摘の「動物実験」については、同研究所においては「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成十八年六月一日付け科発第〇六〇一〇〇五号厚生労働省大臣官房厚生科学課長通知別添)が、同大学においては研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成十八年文部科学省告示第七十一号)が、それぞれ適用され、また、御指摘の「人間での実験」については、同大学及び同研究所いずれにおいても、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針(令和三年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第一号)が適用されるところ、両者において、これらの指針等を遵守することが重要と考えており、「特定一種病原体を用いた研究に関し」これらの倫理指針等の見直しは、現時点では予定していない。
吉川里奈(参政党)
透明性の確保について
BSL-4施設における事故や盗難、流出事案の報告と対応の透明性の確保は、公衆の信頼を維持するために不可欠であると考える。
1 政府はこれらの事態に対処するために、内部基準の見直しや第三者委員会の設置を検討しているのか。
2 新たな法整備が必要と考えるが、その点についての政府の見解を求めたい。
政府
御指摘の「BSL-4施設における事故や盗難、流出事案の報告と対応」については、事故・災害時対応指針において、例えば、「厚生労働省の対応」として「報告聴取、事業所への立入検査」や「専門家を現地に派遣する」こととした上で、事故・災害時対応指針を厚生労働省のホームページにおいて公表しているところであり、また、これに基づき適切に対応した上で、国民に対して必要な情報提供をしていくことにより、御指摘の「透明性の確保」を図ることとしており、御指摘の「内部基準の見直しや第三者委員会の設置」及び「新たな法整備」については現時点で検討していない。
吉川里奈(参政党)
感染事故対策について
事故などにより、万が一感染者が発生した場合、施設内または近隣に隔離施設は用意しているのか。具体的な概要を明らかにされたい。
政府
御指摘の「事故などにより、万が一感染者が発生した場合」は個別の状況により様々であり、また、御指摘の「隔離施設」及び「具体的な概要」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、各「施設」においては、患者の感染状況等に応じて、「施設内」の感染対策や「近隣」の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十四項に規定する第一種感染症指定医療機関等との連携による感染対策が行われるものと承知している。
吉川里奈(参政党)
BSL-4施設の周知徹底について
長崎大学のBSL-4施設の情報提供について、政府は、各府省庁のホームページなどの掲載や、地域とのコミュニケーションを通じて行っているとのことだが、閲覧数や参加人数などの周知効果をどのように把握しているか。政府による記者会見の実施状況も含めて回答されたい。
政府
御指摘の「周知効果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「閲覧数」については、例えば、厚生労働省が実施した「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に関するパブリックコメントに寄せられた意見を踏まえて同省が令和七年一月二十四日に同省のホームページに掲載した「感染症法に基づくBSL4施設の基準」についての「閲覧数」は、同日から同年二月二十八日までの合計で四千四百六十八件であり、また、お尋ねの「参加人数」については、例えば、文部科学省の関与の下、御指摘の「長崎大学のBSL-4施設」の状況等についての情報共有や意見交換等を目的に同大学が設置する「長崎大学高度感染症研究センター実験棟の運用に関する地域連絡協議会」が令和五年七月二十四日から令和七年二月二十八日までに合計六回開催され、その「参加人数」は、延べ二十一人と承知している。
また、御指摘の「政府による記者会見の実施状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和六年十二月二十四日の閣議後記者会見において、福岡厚生労働大臣が御指摘の「長崎大学のBSL-4施設」に関し、記者とやり取りを行っているところである。
令和六年七月十二日から八月十六日に実施された「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」(以下、「本件省令案」という。)に関するパブリック・コメントでは、異例の三万千五百四十一件もの意見が提出された。この意見数から、国民の関心の高さがうかがえる。本件省令案では、日常的に発生する「風邪」を含む急性呼吸器感染症が五類感染症に追加されることが明言されている。パブリック・コメントでは、「急性呼吸器感染症は非常に幅広い病原体・症状を含んでおり、その全てが法による監視が必要な疾患であるとは思えない」との意見や「五類感染症に追加することで、医療費の増大につながるのではないか」など多くの批判が寄せられている。
パブリック・コメントの結果報告(「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する御意見募集の結果について」。以下、「本件結果報告」という。)によると、急性呼吸器感染症を報告する定点医療機関は、これまでどおり週間の患者数の報告が義務付けられており、新たに急性呼吸器感染症病原体定点に対してのみ検体提出が求められる予定であるという。これにより、特に検体提出を行う医療機関の負担が増大する可能性がある。
日本リサーチセンターが二〇一七年一月に行った「風邪に関する調査」によれば、十五歳から七十九歳の日本人は年間平均一・四回風邪を引くとされており、その延べ人数は一億三千九百五十万人と推定されている。風邪の初期症状で医療機関を訪れる人の割合は全体の十三・三パーセントであり、これは千八百五十五万件を超える症例が発生していることを意味する。約三千カ所の定点医療機関のうち、約十パーセントが病原体定点として検体を提供することになり、対象となる症例数の多さから医療従事者への負担が危惧される。
厚生労働省が公表した「医師の勤務環境把握に関する研究」調査によると、令和四年の段階で医師の二十一・二パーセントが月八十時間以上の残業をしており、過労死ラインを超えているとされている。さらに、本件結果報告を見る限り、医療現場にもたらす業務負荷や費用対効果が十分に評価されているとは言い難く、新たな省令が医療現場にさらなる負担をもたらす懸念がある。
以上をふまえ、政府に対し質問する。
北野裕子(参政党)
本件省令の改正に伴う医療機関における業務負荷と、公衆衛生上の利益に対する費用対効果について、政府がどのように分析・評価し、その結果をどの程度公開しているのか。また、この評価が省令策定過程でどのように考慮されているのか、具体的に説明されたい。
政府
お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、令和五年一月二十七日に厚生科学審議会感染症部会(以下「感染症部会」という。)が取りまとめた「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについて」において、「将来的なパンデミックに備えて、季節性インフルエンザウイルス、新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症等を含む急性呼吸器感染症サーベイランスのあり方・・・について、定点医療機関における負担等も考慮しながら本部会において検討を進める」とされたところ、感染症部会において、御指摘の「医療機関における業務負荷」及び「公衆衛生上の利益」についての「評価」を含め、「公開」での議論及び検討が行われた上で、令和六年十月九日に開催された第九十回感染症部会において、「急性呼吸器感染症」を「新たに五類感染症に位置づける」ことが確認されたことを踏まえ、御指摘の「省令」を「策定」した上で、「省令」の施行に向けて、例えば、感染症部会で議論された「医療機関における業務負荷」を「考慮」し、厚生労働省のホームページにおいて「一般の皆様やご協力いただく医療機関の皆様にご理解いただきたいポイント」に関する「Q&A」を掲載しているほか、「定点医療機関」の重点化や「報告」様式の簡素化などの対応について現在検討しているところである。
北野裕子(参政党)
本件省令案に対するパブリック・コメントで寄せられた意見の反対・賛成比率や主な意見の内容を国民にどのように公開し、その意見を政策決定にどう活かしたのか、具体的に示されたい。
政府
御指摘の「パブリック・コメントで寄せられた意見」の中には、質問や必ずしも「反対」又は「賛成」に分類できない意見等も含まれることから、一概にお尋ねの「反対・賛成比率」をお示しすることは困難であるが、お尋ねの「主な意見の内容」については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四十三条の規定に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第百五十六号)の公布の日に、「「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」に関する御意見募集の結果について」として公示しているところであり、「主な意見」も踏まえて、一についてでお答えしたとおり、厚生労働省のホームページへの掲載を行っているほか、必要な対応について検討しているところである。
北野裕子(参政党)
令和四年の時点で医師の二十一・二パーセントが過労死ラインを超える勤務状況にあるとされているが、本件省令案による追加業務がこの問題を悪化させる可能性について、政府はどのように認識し、どのような具体的対策を講じるのか示されたい。
政府
お尋ねの「可能性」については、一についてでお答えしたとおり、感染症部会において、一で御指摘の「医療機関における業務負荷」について議論が行われており、例えば、「RSウイルスに関しましては、大事な感染症ではありますけれども、発熱の有無の中で、冬場など臨床現場にかなりの負担がかかるのではないか」等といった意見もあったところであり、お尋ねの「具体的対策」については、一について及び二についてでお答えしたとおり、厚生労働省のホームページへの掲載を行っているほか、必要な対応について検討しているところである。
北野裕子(参政党)
五類感染症として未知の感染症を監視し早期に検出することが、どのような公衆衛生上の利益をもたらすのか、具体的に示されたい。
政府
お尋ねについては、一についてでお答えしたとおり、感染症部会において、お尋ねの「公衆衛生上の利益」について議論が行われており、例えば、「呼吸器感染症、呼吸器症状を呈する患者さんというのは感染症対策上非常に大切ですし、これまでもいろいろなパンデミックとか再興感染症がそのような患者さんとして発症してきたことは頻度も高いですから、ARIのサーベイランスを採用することにはもちろん賛成」等といった意見もあったところである。なお、一についてで述べた厚生労働省のホームページの「Q&A」において、「新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、[一]こうした流行しやすい急性呼吸器感染症の流行の動向を把握すること、また、[二]仮に未知の呼吸器感染症が発生し増加し始めた場合に迅速に探知することが可能となるよう、平時からサーベイランスの対象とするために、感染症法の五類感染症に位置付けることとしました。これにより、公衆衛生対策の向上につながると考えています。」と公表しているところである。
北野裕子(参政党)
本件省令案により新たに発生する医療費や公衆衛生の改善効果について、国民への周知方法や情報提供の計画を示されたい。
政府
御指摘の「本件省令案により新たに発生する医療費や公衆衛生の改善効果」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、「公衆衛生」の向上及び増進に関しては、四についてでお答えしたとおりである。
北野裕子(参政党)
五類感染症として発見される未知の感染症に対して、政府がどのような対応を行い、それが国民の利益にどのように直結すると考えているのか示されたい。また、これまでの新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえ、未知の感染症において効果的な対応を実現するための具体的な方策があるのか、説明されたい。
政府
前段のお尋ねについては、例えば、令和六年八月二日の閣議後記者会見において、武見厚生労働大臣(当時)が「急性呼吸器感染症を感染症法の五類感染症に位置付けることで、新型コロナウイルス感染症等、個別に把握している感染症以外の急性呼吸器感染症についても、平時から探知できる体制整備が可能となります。この結果、個別に把握していない急性呼吸器感染症についても、迅速に適切な感染症対策の検討を行うことに繋がると考えています」と述べているとおりであり、迅速かつ適切に、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図ることで、公衆衛生の向上及び増進につながると考えている。また、後段のお尋ねについては、御指摘の「未知の感染症」として「急性呼吸器感染症」を「平時から探知できる体制整備が可能」となることで、例えば、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等感染症に該当するかの判断が容易となり、当該感染症に該当する場合には、御指摘の「これまでの新型コロナウイルス感染症への対応の課題を踏まえ」て改定された「新型インフルエンザ等対策政府行動計画」(令和六年七月二日閣議決定)に基づき対応することとなり、同計画に定める「国民生活及び社会経済活動への影響の軽減」等が図られるものと考えている。
長崎大学が稼働を目指す高度安全試験検査施設(バイオセーフティーレベル4施設、以下「BSL―4施設」という。)が、厚生労働省が定める稼働要件を満たし、「合格」の判断を受けたことが令和六年十一月十五日に報道された。BSL―4施設は、研究目的で特定一種病原体を扱う施設であり、平成二十八年十一月の関係閣僚会議において、長崎大学への設置を国策で推進することが決定されていた。特定一種病原体には、致死率が約五十%から約九十%にも及ぶエボラ出血熱の原因となるエボラウイルス等が含まれる。
厚生労働省は、上記病原体の所持者に長崎大学を追加する内容の「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令案」を公表し、令和六年十二月十四日までパブリック・コメントを実施し、年内の施行を目指しているが、住民からは安全性について懸念が表明され、差止訴訟も提起されている。
一方、国立感染症研究所村山庁舎のBSL―4施設は、平成二十七年から稼働し、診断・治療等に関する業務を行っているが、令和元年七月の特定一種病原体等の輸入に関する感染症法に基づく厚生労働大臣指定の際に、武蔵村山市長と同大臣との間で取り決められた確認事項の中で、武蔵村山市以外の適地への移転について検討し、結論を得ることとされた。しかし、移転先が定まらない中、同施設でエボラウイルス等を用いた動物実験を開始したことが、同年三月二十七日の地元住民向けの説明会で明らかになった。
BSL―4施設は、致死率の高い疾病を引き起こすエボラウイルス等の病原体を常時施設内に保管するため、テロや謀略、攻撃、病原体の漏洩事故等が発生した際には、周辺住民の生命・健康等に甚大な影響を与えるおそれがある。加えて、我が国が国内にBSL―4施設を保有する意義や目的、安全対策の内容、漏洩事故や緊急事態発生時の対策、移転先検討状況等が、国民に十分周知されているとは言い難い状況にある。
以上を前提に、以下質問する。
神谷宗幣(参政党)
BSL―4施設について、都内及び長崎での稼働やエボラウイルス等の特定一種病原体の研究に関し、国民の理解や支持が十分ではないと考えるが、政府の見解を示されたい。また、都内のBSL―4施設の移転先検討の進捗状況を明らかにするとともに、BSL―4施設の稼働や移転に関する国民の懸念に対し、どのように対応しているか明らかにされたい。
政府
一の前段について
政府においては、御指摘のような地域の「理解や支持」が得られるよう、関係地方公共団体及び感染症等に係る研究等の専門家から構成される「国立感染症研究所BSL―4施設の今後に関する検討会」が令和二年十二月十一日に取りまとめた「国立感染症研究所BSL―4施設の今後に関する検討会報告書」(以下「報告書」という。)において、「BSL―4施設で感染研職員が作業を行う上で、重要なことの一つに地域の方々の理解を得ることが大切である。それには感染研と地域(住民、学校等の施設関係者、自治体)との継続した、双方向的なコミュニケーションにおいて、BSL―4施設で感染研職員が作業を行うことに対して理解を得ることが重要である。・・・地元との十分なリスクコミュニケーションに基づき理解を得る必要がある」とされていること等も踏まえ、「国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等に関する基本戦略」(令和五年四月七日国際的に脅威となる感染症対策の強化のための国際連携等関係閣僚会議)において、「BSL4施設に関する地域とのコミュニケーションについて、国立感染症研究所が推進している研究活動の積極的な公開をモデルとして、BSL4施設のセーフティ・セキュリティの報告や村山庁舎のアウトリーチ活動に加えて、BSL4施設に係る事業成果等を積極的に発信することにより、BSL4施設運営の透明化を図っていく」等としているところ、これに基づき適切に対応することとしている。具体的には、地域住民や「BSL4施設」関係者等を構成員として「地域とのコミュニケーション」を図る場として、御指摘の「都内」については、「BSL―4施設」を「稼働」している国立感染症研究所村山庁舎の活動に関し、厚生労働省が「国立感染症研究所村山庁舎施設運営連絡協議会」(以下「施設運営連絡協議会」という。)を設置し、また、御指摘の「長崎」については、今後「BSL―4施設」を「稼働」する予定である長崎大学の活動に関し、文部科学省の関与の下、同大学が「長崎大学高度感染症研究センター実験棟の運用に関する地域連絡協議会」(以下「地域連絡協議会」という。)を設置し、それぞれの施設の活動状況等についての情報共有や意見交換等が行われているところである。また、同研究所及び同大学それぞれのホームページにおいては、施設運営連絡協議会及び地域連絡協議会それぞれの開催状況について公表されており、政府においても、必要に応じて、これらについて、関係府省庁、同研究所、関係地方公共団体及び感染症に係る研究の専門家から構成される「感染症研究拠点の形成に関する検討委員会」(以下「検討委員会」という。)において進捗を確認し、また、首相官邸ホームページにおいて検討委員会の資料として公表しているほか、厚生労働省及び文部科学省のホームページにおいても、これらに関する情報を公表しているところである。したがって、お尋ねのように「国民の理解や支持が十分ではない」とは一概には言えないと考えており、いずれにせよ、政府として、引き続き、「国民の理解や支持」を得られるよう努めてまいりたい。
一の後段について
お尋ねの「都内のBSL―4施設の移転先検討の進捗状況」については、これを明らかにすることで、今後の議論や検討に支障を来すおそれなどがあり、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条第五号に掲げる不開示情報に該当するものと考えられるため、現時点で公開することは差し控えたい。
また、お尋ねの「国民の懸念」への「対応」については、一の前段についてでお答えしたとおりであり、国民の理解や支持を得られるよう努めていくこととしている。
神谷宗幣(参政党)
エボラウイルスは主にアフリカで流行しており、日本国内での流行歴がない。この状況下で、エボラウイルスを用いた動物実験や研究を国内で行う必要性と、そのために国の資源を投入する理由について、政府はどのように説明するか示されたい。また、国内にBSL―4施設を保有することの意義及び国民にとっての便益をそれぞれ明らかにされたい。
政府
御指摘の「BSL―4施設」は、必ずしも御指摘の「エボラウイルスを用いた動物実験や研究」のみを行うわけではないが、いずれにせよ、お尋ねの「必要性」及び「意義」については、検討委員会が平成二十九年二月十七日に取りまとめた「高度安全実験施設(BSL4施設)を中核とした感染症研究拠点の形成について」(以下「取りまとめ」という。)において、「人の往来が盛んであるグローバル社会において、感染症は、限定的な地域での流行に留まらず、国内でのまん延、さらには国境を越えて国際社会全体への感染拡大が懸念されている。また、世界各地における森林開発、気候変動等により、動物等を媒介した感染症への感染リスクも増大している」、「国内におけるBSL4施設を活用した基礎研究及び人材育成の必要性が我が国の研究者の間で認識されている」及び「BSL4施設の活用により実施可能となる研究開発及び求められる機能等実施した調査の結果では、高病原性ウイルスを対象として、」「ウイルスの生態および伝播経路を解明すること(疫学研究)、」「ウイルスと宿主因子の相互作用を理解すること(感染機構研究)、」「ウイルス感染による宿主の応答・病態を解析すること(病態研究)、」「ワクチン、診断法および抗ウイルス薬を開発すること(医療応用研究)の各研究過程に沿った研究課題が示された」としているとおりであり、また、報告書において、「世界における人、モノの往来が活発となった現在、一種病原体の国内への侵入と、これによる感染症はいつでも発生する危険性がある。また、バイオテロ病原体として一種病原体が使用される危険性もある。このような状況の中で、BSL―4施設は、(一)感染症発生時の検査診断による健康危機管理への対応(検査法の開発、疑い患者の検査実施、確定患者の随時検査、接触者等に対する病原体疫学調査、患者の退院の可否に係わる検査等)、(二)感染症対策に必要な病原体等に関する科学情報を実験等により収集分析(基礎研究)、(三)感染症の診断、治療、予防に係わる具体的な技術の研究開発(応用研究)(中略)の目的から設置は必須である」、「新たな病原体の検査診断法の開発や精度の向上等検査診断に関連する研究、ワクチンや治療法の開発などの基盤・応用研究が可能である規模を有する施設であることが求められる」等とされていると承知しており、政府としても同様に考えている。したがって、お尋ねの「国の資源を投入する」必要があると考えており、また、「BSL―4施設」の設置により「健康危機管理への対応」等が図られ、お尋ねの「国民にとっての便益」になるものと考えている。
神谷宗幣(参政党)
都心部や住宅地におけるBSL―4施設の稼働について、事故発生時のリスク管理と住民保護のための安全対策の具体的内容を明らかにされたい。また、事故発生時の影響を考慮に入れた安全性を最優先にした立地選定が行われているか示されたい。
政府)
三の前段について
お尋ねについては、御指摘の「都心部や住宅地」であるか否かにかかわらず、例えば、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「感染症法」という。)第五十六条の三第二項に規定する特定一種病原体等所持者については、感染症法第五十六条の十八第一項に基づく感染症発生予防規程の作成や、感染症法第五十六条の二十九に基づく災害時の応急措置等が義務付けられているほか、「特定病原体等に係る事故・災害時対応マニュアル」(令和五年九月厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課)において、「特定病原体等所持者・・・は、災害の発生により所持する特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延した場合又は当該特定病原体等による感染症が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合は、直ちに、状況に応じて、以下の応急の措置を講じるものとする。①特定病原体等取扱施設又は特定病原体等が容器に収納されているもの・・・に火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合、これを発見した者は消火又は延焼の防止に努めるとともに、直ちに、あらかじめ規定した手順に従い、火災が発生したことを遅滞なくあらかじめ指定された者に報告する。あらかじめ指定された者は、火災発生の報告を受けたときは、直ちにその旨を消防署又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十四条の規定により市町村長の指定した場所に通報する。その際、通報した消防署等から何らかの指示等があった場合には、これに従い適切な措置を講じるものとする。②特定病原体等による感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、あらかじめ指定された者は特定病原体等取扱施設の内部にいる者に、運搬中の災害発生時においてもあらかじめ指定された者は病原性輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者に避難するよう警告する。③必要に応じて、病原体等取扱主任者等は特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等がある場所の周囲には、ロープを張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置を講ずるよう努める」等としているところ、これらに基づき対応されることとなっている。
三の後段について
御指摘の「立地選定」に当たっては、御指摘の「事故発生時の影響を考慮に入れた安全性」を勘案することはもとより、取りまとめにおいて、「立地については、世界最高水準の安全性の確保を目指した施設の管理運営を円滑に行うとともに、大学等の研究機関や感染症指定医療機関が近くに存在すること、安定的なインフラが存在すること、及び警察・消防との連携を含めたセキュリティサービスが充実していることが必要である」としているとおりであり、また、報告書において、「厚生労働本省と近距離であることが必要である」、「特定感染症病床を有し、一類感染症(感染症法第六条第二項)を診療する機会が多いと考えられる国立国際医療研究センターと病原体の確定診断を行うBSL―4施設との距離が現行よりも遠距離にならないようにすることが望ましい」等とされていることなどを踏まえ、様々な事情を総合的に勘案の上、適切に対応することとしており、いずれか一つの事情を御指摘のように「最優先」に考慮するわけではない。
神谷宗幣(参政党)
現在のBSL―4施設に関する情報公開と透明性の確保に向けた取組について、政府の方針を示されたい。また、研究内容やリスク管理の手法を国民にどのように伝え、国民の懸念や意見をどのように取り入れているか示されたい。
政府
四の前段について
お尋ねについては、一の前段についてでお答えしたとおりである。
四の後段について
「研究内容やリスク管理の手法を国民にどのように伝え」ているかとのお尋ねについては、一の前段についてで述べた「地域とのコミュニケーション」や「公表」の中で、必要な情報提供を行っているところであり、また、「国民の懸念や意見をどのように取り入れているか」とのお尋ねについては、例えば、令和六年十一月十五日から同年十二月十四日まで実施した、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関する御意見の募集について」等を通じて、国民から「BSL―4施設」に関する御意見を頂きながら、「BSL―4施設」の在り方の検討に当たっての参考としているところである。
神谷宗幣(参政党)
BSL―4施設において事故や緊急事態が発生した際、政府はどのような対応を計画・準備しているか示されたい。
政府
お尋ねについて、御指摘のように「事故や緊急事態が発生した際」には、「特定病原体等に係る事故・災害時対応指針」(令和五年九月厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課)において、例えば、「厚生労働省感染症対策課は、・・・特定病原体等所持者・・・から災害応急時措置届出書の提出やその他の方法により災害発生の通報を受けたときは、災害の状況把握に努め、管轄の地方厚生局に連絡するとともに、災害の状況に応じて、本省又は地方厚生局の担当官を現地に派遣し、特定病原体等所持者・・・からの報告聴取、事業所への立入検査その他の対応を行うものとする。・・・災害時の応急の措置に関し緊急の必要があると認めるときは、法第五十六条の三十七の規定に基づき特定病原体等所持者・・・に対し、特定保管場所の保管場所の変更、滅菌等の必要な措置を講ずるよう命令を行うものとする」等としているところ、これに基づき適切に対応することとしている。
神谷宗幣(参政党)
国内のBSL―4施設で得られた研究成果や権利の帰属及び取扱いについて、政府の方針を示されたい。また、外国からの資金提供等により、研究成果が国外に移転する可能性や、それに対処する具体的な枠組みについて回答されたい。
政府
六の前段について
御指摘の「国内のBSL―4施設で得られた研究成果や権利の帰属及び取扱い」については、各施設ごとに定められており、国立感染症研究所に関しては、「厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規程」(平成十五年三月三十一日厚生労働省大臣官房厚生科学課長決定)及び「国立感染症研究所職務発明等規程」(平成十三年三月八日国立感染症研究所部長会議決定)において、また、長崎大学に関しては、「長崎大学職務発明規程」(平成十六年規程第七十三号)、「長崎大学研究成果物等取扱規程」(平成十六年規程第七十五号)等において、それぞれ定められているとおりである。
六の後段について
お尋ねの「可能性」については、仮定の質問であり、お答えを差し控えたいが、いずれにせよ、御指摘のように「移転する」ことがないようにするためのお尋ねの「対処する具体的な枠組み」については、国立感染症研究所に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする」と規定されているほか、「厚生労働省所管の国立試験研究機関における職務発明等規程」において「職務発明者及び当該発明の内容を知り得た関係職員は、国及び職務発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない」と、「国立感染症研究所職務発明等規程」において「職務発明者及び当該発明の内容を知り得た関係職員等は、国及び職務発明者の利害に関係ある事項について、必要な期間中、その秘密を守らなければならない」とされているところであり、また、長崎大学に関しては、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第十八条において「国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする」と、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十一条第二項において「大学・・・は、その研究開発の成果について、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる国外流出の防止に努めるものとする」と規定されているほか、「長崎大学共同研究規程」(平成十六年規程第六十五号)において「本学又は共同研究者は、共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない」とされているところである。
厚生労働省の統計によると、日本の精神病床数は、現在、三十万床を超え、入院患者は二十六万人に上る。そして、このうち約半数は、本人の意思によらない措置入院及び医療保護入院となっている。日本の精神病院のベッド数は、世界でも突出しており、全世界の五分の一の精神病床が日本にあるとのデータもある。諸外国と比べ、平均在院日数も長く、入院患者の六割強が一年以上在院し、そのうちの五割強が五年以上在院している。
二〇〇四年に厚労省が「精神保健医療福祉の改革ビジョン」の一環として、「入院医療中心から地域生活中心へ」との理念を打ち出し、「受入条件が整えば退院可能な者約七万人について、十年後の解消を図る」とした。しかし、十年後の到達点は、目標値の半分強である四万人減にとどまっている。結果として、本人の意思によらない措置入院及び医療保護入院数もわずかな減少に過ぎないものとなっている。
二〇二一年十月、日本弁護士連合会は「精神障害のある人の尊厳の確立を求める決議」を出した。同決議では、精神障害のある人に対する障害を理由とした人権侵害の根絶を達成するために、現行法制度の抜本的な改革を行い、精神障害のある人だけを対象とした強制入院制度を廃止して、これまでの人権侵害による被害回復を図り、精神障害のある全ての人の尊厳を保障すべきであるとされている。
厚労省は、二〇二二年三月に医療保護入院について、制度の将来的な廃止も視野に入れ、縮小する方向での検討に入ったが、同年五月には、一転、有識者検討会の報告書案から当初盛り込んでいた「将来的な廃止」「縮減」との文言を削除し、方針を後退させた。
二〇二二年九月には、国連の障害者権利委員会が障害者権利条約の国内実施状況に関する審査において、日本政府に対して、強制入院の廃止や、入院中の全ケースの見直し、インフォームドコンセントの確保、地域社会で必要な支援とともに自立した生活を育むことなどを要請している。
日本の医療保護入院の要件は、精神保健指定医の診察及び家族等の同意のみが必要で、本人の同意は不要であり、本人の意思を担保する制度も整備されていない。例えば、韓国では、医療保護入院には、保護義務者二人の同意と精神科専門医一人の診断が必要とされ、日本の制度よりも厳格であった。しかし、二〇一六年九月には、精神科医や家族の悪用を防ぐ手立てに欠けるなど患者の人権保護が不十分であるとして、本人の同意のない精神科への強制入院が違憲であるとの判決が韓国憲法裁判所で下された(Constitutional Court of Korea 2014Hun-Ka9、以下「韓国憲法裁判所判決」という。)。
また、米国では、重症精神疾患者の強制入院は裁判官が決定し、英国やオーストラリアでは精神保健審判裁判所等が決定するなど、司法審査が導入されている。
以上を見るなら、諸外国と比較して我が国の保護入院における患者の人権保護前進に向けた取組は、遅れていることが明らかである。
また、政府は、家族等の同意が要件となる理由として、「原則として、本人についての情報をより多く把握していることが期待できる」(内閣衆質一九三第一四〇号)旨答弁しているが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第三十三条では、「家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる」とされているのに、同意する家族の優先順位は定められていない。この点について、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」(第百八十三回国会閣法第六五号)に対する衆議院厚生労働委員会の附帯決議(以下「精神保健福祉法案衆議院附帯決議」という。)では、「同意を得る優先順位等をガイドラインに明示し、厳正な運用を促すこと」が求められているが、このガイドラインはいまだ制定されていない。
以上を踏まえ質問する。
神谷宗幣(参政党)
日本は諸外国に比べ、精神病床数が多く、入院期間も長い傾向にある。政府は改善を図るとしているが、取組が諸外国と比べて遅れているのはどのような理由があると考えられるか、示されたい。
政府
お尋ねについては、精神科医療の提供体制等は国により異なることから、日本と諸外国の取組を単純に比較することは困難であり、一概にお答えすることは困難である。
神谷宗幣(参政党)
今後、「入院医療中心から地域生活中心へ」との理念のもと、病床を減らしていくとすると、民間の精神科病院の再編が必要となると思われるが、その経営転換に係る政府の計画と、財政的助成措置などについて、説明されたい。
政府
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般に、精神科病院の経営の在り方については、各精神科病院において検討されるものと考えている。
また、現時点ではお尋ねの「その経営転換」に係る「財政的助成措置」はない。
神谷宗幣(参政党)
精神保健福祉法第三十三条が想定する「家族等」について、患者とその家族との関係は多様で、同居していない場合や関係が良好でない場合もあると思われる。実際に、同居している配偶者がいるにもかかわらず、本人とは疎遠であった長男が同意を行い、トラブルが発生した事例があるとも聞く。これらを踏まえ、同意権者について、優先順位を設けることを検討することが肝要と思われるが、現状での政府の認識を示されたい。
政府
御指摘の「家族等」と精神障害者との関係については様々な状況があることから、御指摘の「同意権者」について一律に「優先順位を設けること」は考えていないが、「医療保護入院における家族等の同意に関する運用について」(平成二十六年一月二十四日付け障精発〇一二四第一号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課長通知)により、都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)を通じて精神科病院に対して、「医療保護入院においては、その診察の際に付き添う家族等が、通例、当該精神障害者を身近で支える家族等であると考えられることから、精神科病院の管理者・・・は、原則として、診察の際に患者に付き添う家族等に対して入院医療の必要性等について十分な説明を行い、当該家族等から同意を得ることが適当である」と示しているところである。
なお、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。)第五条第二項ただし書の規定により、精神障害者に対して訴訟をしている者や身体に対する暴力を行った者等については、同項に規定する家族等から除かれているところである。
神谷宗幣(参政党)
措置入院及び医療保護入院後、患者本人の同意なく投薬がされるケースがあると聞く。措置入院及び医療保護入院後の治療方針や投薬に関して、どのようなインフォームドコンセントがなされているか、政府は把握しているか。また、国としてはどのような在り方が望ましいと考えているか、示されたい。
政府
お尋ねの「どのようなインフォームドコンセントがなされているか」について、個々の精神科病院における状況は把握していないが、政府としては、良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針(平成二十六年厚生労働省告示第六十五号)において、「精神医療においても、インフォームドコンセント(医師等が医療を提供するに当たり適切な説明を行い、患者が理解し同意することをいう。・・・)の理念に基づき、精神障害者本位の医療を実現していくことが重要であり、精神障害者に対する適切な医療及び保護の確保の観点から、精神障害者本人の同意なく入院が行われる場合においても、精神障害者の人権に最大限配慮した医療を提供すること」等を基本的な考え方として定め、都道府県等を通じて精神科病院に対して示しているところである。
神谷宗幣(参政党)
「精神保健医療福祉の改革ビジョン」では「入院医療中心から地域生活中心へ」を基本方策としているが、この理念を具体化するには精神疾患患者の地域での生活を支え、多様化するニーズにも対応するため、退院後の生活環境相談員となる精神保健福祉士等の役割が益々重要となると思われる。役割の増大が明らかである要員の増員等の施策について、具体的に示されたい。
政府
お尋ねの「役割の増大が明らかである要員の増員等の施策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、精神保健福祉士は、精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二条の規定により、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院等において精神障害の医療等を受けている者の相談援助を行うことを業としており、精神科病院に入院する者の早期の地域生活への移行に向けた取組の推進を図る上で重要な役割を担っているものと考えている。このため、令和元年に精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知見を有する有識者等から構成される「精神保健福祉士の養成の在り方等に関する検討会」で議論を行い、精神障害者の状況に応じ、より的確に相談援助を行うことができる人材を育成するため、精神保健福祉士の養成カリキュラムの充実等の取組を行っているところであり、今後とも、必要な取組を進めてまいりたい。
神谷宗幣(参政党)
精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神疾患と精神障害者に対する地域社会、国民の間での正しい理解の促進が必要であると思われる。政府はこの課題について、いかなる施策を考え具体化しているのか。今後の課題を含め、示されたい。
政府
御指摘の「精神障害者の地域生活への移行を促進するため、精神疾患と精神障害者に対する地域社会、国民の間での正しい理解の促進が必要である」という課題について、政府としては、例えば、令和三年度から、「心のサポーター養成事業」において、メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識と理解を持ち、地域や職域でメンタルヘルスの問題を抱える者及びその家族等に対して可能な範囲で支援する者を「心のサポーター」として養成するための研修等を実施しており、今後、「心のサポーター」の認知度を向上させ普及を図ることが重要であると考えている。
このほか、ホームページでの周知や啓発イベントなどの取組を通じて、精神障害に関する正しい知識を普及させるとともに、国民一人一人の理解が深まるよう、引き続き必要な取組を進めてまいりたい。
神谷宗幣(参政党)
国際的な機関も含めた人権関連団体から我が国に対し、本人の同意に基づかない入院を廃止すべきとの勧告等がなされている。これらを政府はどのように受け止めているか。これらを受けた具体的な施策の準備があれば示されたい。
政府
御指摘の「国際的な機関も含めた人権関連団体から我が国に対し、本人の同意に基づかない入院を廃止すべきとの勧告等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「本人の同意に基づかない入院」については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第百四号。以下「令和四年改正法」という。)附則第三条において、「政府は、精神保健福祉法の規定による本人の同意がない場合の入院の制度の在り方等に関し、精神疾患の特性及び精神障害者の実情等を勘案するとともに、障害者の権利に関する条約の実施について精神障害者等の意見を聴きつつ、必要な措置を講ずることについて検討するものとする」とされており、これに基づいて検討してまいりたい。
神谷宗幣(参政党)
韓国憲法裁判所判決の内容について、我が国においても精神保健福祉法の改正を検討する際の重要な指標となると思われる。政府は、この判決の内容について今後の精神保健福祉行政を考える上でどのような意義があると考えるか。
政府
お尋ねについては、精神科医療の提供体制等は国により異なることから、御指摘の「判決の内容」について単純に評価することは困難であり、一概にお答えすることは困難である。
神谷宗幣(参政党)
精神保健福祉法案衆議院附帯決議では、「精神障害者の意思決定への支援を強化する観点からも、自発的・非自発的入院を問わず、精神保健福祉士等専門的な多職種連携による支援を推進する施策を講ずること。また、代弁者制度の導入など実効性のある支援策について早急に検討を行い、精神障害者の権利擁護の推進を図ること。」としている。ここで指摘されている代弁者制度について、政府はどのような検討が行ってきたか。今後、代弁者制度ないしこれに準ずる本人の同意を担保する何らかの制度を導入する方針を持っているのか。
政府
御指摘の「精神保健福祉法案衆議院附帯決議」においては、「代弁者制度の導入など実効性のある支援策について早急に検討を行い、精神障害者の権利擁護の推進を図ること」とされており、当該支援策の在り方について検討するため、平成二十六年度障害者総合福祉推進事業「入院中の精神障害者の意思決定及び意思の表明に関するモデル事業」を実施したところ、同事業等により蓄積されたノウハウ等も踏まえ、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知見を有する有識者等から構成される「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」で令和四年六月九日に取りまとめられた報告書において、「非自発的入院による患者・・・は、閉鎖処遇に置かれており、外部との面会交流が難しくなる。家族からの音信がない市町村長同意による医療保護入院者については、医療機関外の者との面会交流が、特に途絶えやすくなる。(中略)市町村長同意による医療保護入院者を中心に、精神科病院の理解のもと、精神科病院に入院する患者を訪問し、相談に応じることで、医療機関外の者との面会交流を確保することが必要となる」とされたところである。これを踏まえて検討が行われ、令和四年改正法による改正後の精神保健福祉法第三十五条の二第一項に規定する入院者訪問支援事業が創設され、同項に規定する入院者訪問支援員が入院中の精神障害者本人の希望により精神科病院を訪問し、本人の話を丁寧に聴くとともに、必要な情報提供等を行うものとされたところであり、同事業を適切に実施しながら、引き続き入院中の精神障害者の権利擁護を図ってまいりたい。
神谷宗幣(参政党)
米国や英国、オーストラリアなどでは、強制入院に関し、司法審査を導入している。我が国においても、強制入院の際、司法審査と同等の要件を導入するべきではないか。
政府
お尋ねについては、日本と諸外国における精神科医療の提供体制等は異なることから、御指摘の「司法審査」を日本に導入することについては慎重に検討すべきものと考えているが、必要に応じて情報の収集に努めてまいりたい。
神谷宗幣(参政党)
我が国で措置入院及び医療保護入院となっている外国人の国籍別人数及び過去五年間の推移を示されたい。
政府
お尋ねの「国籍別人数及び過去五年間の推移」については、把握していない。
質問1)新型コロナワクチンの診療記録の保存期間
新型コロナワクチンの健康被害は長期間にわたる可能性があるにもかかわらず、政府は行政記録や診療録の保存期間を延長しないため、過去の薬害と同じように、診療記録が破棄され、救済の壁になる可能性がある。
質問2)予防接種台帳の保存期限
将来に備えて、いくつかの地方自治体では予防接種台帳の保存期限を延長しているが、政府はどのくらいの数の地方自治体が延長しているかを把握しておらず、知らない地方自治体のために延長が可能であることを周知する予定はない。
質問3)予防接種健康被害救済制度の平均審査期間
半年から一年程かかる。
質問4)予防接種健康被害救済制度申請の相談に応じる保健福祉相談員
減少している。(2020年, 57名、2021年, 56名、 2022年, 58名、2023年, 53名)
質問5)予防接種健康被害救済制度の認知と書類準備の理解促進
厚生労働省は2021年12月17日に「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(初版)」 を作成し、その中で当該制度の趣旨や手続の流れ等について詳細に記載し、当該制度の申請の窓口である市町村に対して周知した。
オックスフォード大学が運営するOur World in Dataによれば、令和五年十月十九日現在、人口百人当たりの新型コロナワクチン接種回数は、日本が世界一となっている。そのような中、同年九月二十日からは、希望するすべての国民に対し、XBB対応ワクチンの接種が始まった。これは、多い人では、七回目の接種機会となる。
mRNAワクチンの頻回接種により自己免疫疾患発症のリスクが高くなることについては、令和五年三月九日付け第二百十一回国会質問第三七号で私が指摘したとおりである。
このような状況からすれば、今後もワクチン接種後の健康被害を訴え、国の予防接種健康被害救済制度で申請を行う人が増加することが想定される。
この点、新型コロナワクチン接種の際に作成される行政記録は、予防接種法及び予防接種法施行規則に基づき、また、診療録は医師法に基づき、いずれも五年間と定められている。
新型コロナワクチンは、治験中であり、過去、人類がこれほど多く短期間に接種した歴史はない。また、前述したように、接種回数を重ねるたびに副作用、後遺症発現のリスクが高まることに鑑みれば、長期的な影響を調査する必要もある。過去の薬害では、診療録の破棄が、救済の壁となることがままあったことに鑑みれば、新型コロナワクチン接種の診療録は、万が一の事態に備え、格別の措置を講じるべきである。
以上を前提に、以下質問する。
神谷宗幣(参政党)
過去に例のない規模の健康被害が生じていることに鑑み、国としては、新型コロナワクチン接種に係る行政記録や診療録の保存期間の延長をすることを検討しているか。検討している場合、いつごろまでに判断される予定か。
政府
御指摘の「新型コロナワクチン接種に係る行政記録や診療録の保存期間の延長をすること」は、現時点では検討していない。
神谷宗幣(参政党)
千葉県我孫子市や東京都小平市など複数の地方自治体では、将来、健康被害が発生する事態に備え、予防接種台帳の保存期間を十年ないし三十年に延長しているようである。政府としては、どのくらいの数の地方自治体が予防接種台帳の保存期間に関する対応を行っているか把握しているか。政府として、地方自治体に対し、予防接種台帳の保存期間延長が可能であることについて周知する予定はあるか。
政府
御指摘の「地方自治体が予防接種台帳の保存期間に関する対応を行っているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に市町村における予防接種台帳の保存期間の延長を行っているかについてのお尋ねであれば、政府として把握していない。また、御指摘の「予防接種台帳の保存期間」については、「「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き」の改訂について」(令和五年九月二十日付け感発〇九二〇第一号厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部長通知)の別添「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(十九版)」において、「新型コロナワクチンの接種の対象者について、・・・予防接種台帳を作成し、・・・少なくとも五年間は適正に管理・保存すること」と市町村に対して周知しているところであり、これに加えて、御指摘の「予防接種台帳の保存期間延長が可能であることについて周知する予定」は、現時点ではない。
神谷宗幣(参政党)
新型コロナワクチン接種で健康被害を受けた人は、迅速な被害救済を望んでいるところ、予防接種健康被害救済制度の申請件数が急増している。これに関し、過去五年間の疾病・障害認定審査会の平均審査期間の推移は如何。また、予防接種健康被害救済制度申請の相談にあたる、同審査会の人員体制は、新型コロナワクチン接種開始前と比べどの程度増加したか。
政府
お尋ねの「疾病・障害認定審査会の平均審査期間の推移」については、調査に時間を要するため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「予防接種健康被害救済制度の申請」が市町村から都道府県を経由して厚生労働省に進達され、厚生労働大臣が認定を行うまでの期間について言えば、令和五年三月十六日の衆議院内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会において、加藤厚生労働大臣(当時)が「市町村から国に上がってきて、実際、結論が出るまでについて、大半、半年から一年程度の期間を要しております」と答弁しているところである。また、お尋ねの「同審査会の人員体制」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、疾病・障害認定審査会感染症・予防接種審査分科会(以下「分科会」という。)に属する委員の数は、御指摘の「新型コロナワクチン接種開始前」における直近の第百四十回分科会が開催された令和三年二月五日時点で二十四名であり、第百六十四回分科会が開催された令和五年十月十六日時点で二十四名である。これに加えて、新型コロナウイルス感染症に関する「予防接種健康被害救済制度の申請」に対する審査の迅速化を目的に、新たに分科会に同年一月に新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第一部会(以下「第一部会」という。)及び新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第二部会(以下「第二部会」という。)を、同年六月に新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第三部会(以下「第三部会」という。)を設けたところであり、第一部会に属する委員の数は、直近の第十回第一部会が開催された同年十月六日時点で九名であり、第二部会に属する委員の数は、直近の第九回第二部会が開催された同年九月二十七日時点で九名であり、第三部会に属する委員の数は、直近の第五回第三部会が開催された同年十月二十三日時点で九名である。
神谷宗幣(参政党)
現場では、予防接種健康被害救済制度の申請にあたって、相談に応じることのできる保健福祉相談員の数が不足しているとの声がある。過去五年間の保健福祉相談員の人員体制は、新型コロナワクチン接種開始前と比べどの程度増加したか。
政府
お尋ねの「過去五年間の保健福祉相談員の人員体制」については、厚生労働省から予防接種健康被害者保健福祉相談事業を委託している公益財団法人予防接種リサーチセンターに確認したところによれば、令和元年度末時点で五十五名、令和二年度末時点で五十七名、令和三年度末時点で五十六名、令和四年度末時点で五十八名、令和五年九月末時点で五十三名である。なお、御指摘の「予防接種健康被害救済制度の申請にあたって、相談に応じる」ことについては、市町村の窓口等において行われているところ、同省において市町村に対し、コールセンター又は相談窓口の設置等により相談体制の構築を進めるよう周知しているところである。
神谷宗幣(参政党)
第三十七回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会の資料によれば、予防接種健康被害救済制度の申請にあたって、制度の認知・理解や書類の準備に苦労したと感じる人が相当数いたとのことである。この結果を受けて、政府は、どのような方策を講じたか。
政府
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)に基づく健康被害救済制度については、従来から、厚生労働省のホームページや、接種を受ける方に配布するリーフレット等の様々な媒体を通じて、広く周知を図ってきたところであるが、令和二年一月二十七日に開催された御指摘の「第三十七回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会の資料」に記載の「認定を受けた者のうち、健康被害救済制度の申請に当たって、制度の認知・理解や書類の準備等に苦労したと感じた者が相当程度存在した」こと等も踏まえつつ、新型コロナウイルス感染症への対応として、同省において、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きについて」(令和二年十二月十七日付け健発一二一七第四号厚生労働省健康局長通知)の別添「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(初版)」を作成し、その中で当該制度の趣旨や手続の流れ等について詳細に記載し、当該制度の申請の窓口である市町村に対して周知したところである。予防接種後に健康被害を受けた方々が、当該制度に基づく救済の申請を円滑に行っていただけるよう、今後とも、自治体や医療機関と緊密に連携しながら、より一層の周知に取り組んでまいりたい。
質問1)ファイザー社から日本政府への説明
2023年3月の時点で、ファイザー社と米国食品医薬品局(FDA)は新型コロナワクチンが妊婦・胎児及び授乳中の乳児に対し て潜在的な影響を持つ可能性を認識していたが、政府はその説明を受けていない。
質問2)新型コロナワクチンの安全性に関する厚労省の認識
厚生労働省は米国食品医薬品局(FDA)のデータファイルを認知しているにも関わらず、新型コロナワクチンの安全性について重大な懸念は報告されていないと認識している。
質問3)妊婦への新型コロナワクチン接種
ドイツにおいて「妊婦に対するブースター接種を推奨しない」とする勧告が出ていることを日本政府は承知しているが、引き続き、日本では妊婦に対する接種を推奨していく。
質問4)新型コロナワクチンの流産リスクに関する厚労省の認識
厚生労働省が2023年3月10日に発出した「ワクチン接種が流産の原因となるというのは誤情報である」とする文書は厚生労働省の独自見解であり、この文書を撤回したり、見直すべきとは考えていない。
質問5)新型コロナワクチンの乳児リスクの認識
厚生労働省のウェブサイトでは「ワクチン自体が母乳に移行する可能性は低く、万が一mRNAが母乳中に存在しても、子どもの体内で消化されることが予想され、影響を及ぼすことは考えにくいと報告されています」と記載されているが、これは厚生労働省の独自見解であり、ファイザー社がFDAに提出した報告書の内容を踏まえても、変更するつもりはない。
質問6)妊婦・乳児の副反応疑い
2023年2月17日から2025年3月12日の期間で、政府は以下の副反応疑い報告を認識している。妊婦:102件、乳児(授乳を介した曝露):3件
質問7)新型コロナワクチンの特例承認
免疫力が低下する妊婦へのワクチン接種は禁止されているのに新型コロナワクチンが特例承認されているのは、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の特例承認に係る報告書」において、妊婦28件で9件が非重篤反応であり、乳児39件で4件が非重篤反応であったことを、踏まえたものである。
質問8)新型コロナワクチンの長期的な検証
お尋ねの「長期的な検証」の意味するところが必ずしも明らかではない。
これは、FDAが裁判での開示命令に従って公開したデータファイル(ファイザー社が新型コロナワクチンの承認申請のためにFDAに提出したファイル。以下「本件文書」という。)から発覚した内容であり「妊娠と授乳に関する累積的レビュー」(PREGNANCY AND LACTATION CUMULATIVE REVIEW)として、薬剤開発時点から令和三年二月二十八日までの症例に関する調査データが報告されている。
この調査によれば、四百五十八件の妊娠中の新型コロナワクチンの曝露に関し、疼痛(百一例)、頭痛(五十七例)、自然流産(五十一例)、疲労(四十三例)、発熱(二十六例)、悪寒(二十四例)、筋肉痛(二十三例)、悪心(二十二例)、関節痛(十六例)、浮動性めまい(十五例)、倦怠感(十二例)、リンパ節症(十一例)、無力症(十一例)が生じているとされている。
このうち、流産は稽留流産等も含めると五十三件あり、流産を免れても、早産で出生した六人に有害事象が認められ、うち二人が死亡し、一人に深刻な後遺症が残っている。これらの事象は、胎盤を通過した新型コロナワクチンあるいは新型コロナワクチンの成分であるスパイクタンパク質が、胎児に影響した可能性があることを示唆している。
また、二百十五件の授乳中の新型コロナワクチンの曝露に関し、発熱や頭痛、下痢などの様々な有害事象が見られ、中には、易刺激性や発疹、血管浮腫など十件の重篤な有害事象が発生し、うち六件は乳児で報告されている。これらの事象は、母乳を介して、乳児に新型コロナワクチン又は新型コロナワクチンの成分であるスパイクタンパク質が影響を及ぼす可能性を示唆している。
以上の事実を踏まえ、以下質問する。
神谷宗幣(参政党)
政府は、ファイザー社とFDAが、令和三年三月の時点で、新型コロナワクチンが妊婦、胎児及び授乳中の乳児に対して潜在的な影響を持つ可能性を事前に認識していたという事項について、これまでの複数回にわたるファイザー社との新型コロナワクチン購入契約時に説明を受け認識していたか。
政府
お尋ねの「ファイザー社とFDAが、令和三年三月の時点で、新型コロナワクチンが妊婦、胎児及び授乳中の乳児に対して潜在的な影響を持つ可能性を事前に認識していたという事項」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ファイザー社との感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)附則第七条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の購入契約に係る交渉に際して、同社が米国食品医薬品局に御指摘の「本件文書」を提出したという事実及び当該文書の内容についての説明を受けたことはない。なお、当該交渉は、当該新型コロナワクチンが医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)による承認(以下単に「承認」という。)を受けることを前提として行ったものである。
神谷宗幣(参政党)
前記一の事実について、現在はどのように認識しているか。
政府
お尋ねの「前記一の事実について、現在はどのように認識しているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナワクチンについては、その有効性とリスクも含めた安全性を比較衡量し、薬事・食品衛生審議会における議論を経て、承認を行ったものであり、新型コロナ予防接種については、承認を受けた新型コロナワクチンについて厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において有効性及び安全性に関する議論を行った上で、新型コロナ予防接種の実施が新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため必要であること、新型コロナ予防接種の有効性及び安全性に関する知見、諸外国における接種状況等を総合的に考慮し、対象者を決定して、実施しているものである。また、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、予防接種法第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品医療機器等法第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナワクチンの製造販売業者等から同大臣に報告されており、これらの制度により収集した情報等に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において、専門家による議論が行われ、新型コロナワクチンの安全性について評価を行っているところであり、令和五年四月二十八日の合同部会において、現時点では「ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくこと」としてよいこととされている。また、公表されている学術論文等から収集した新型コロナワクチンの安全性等に係る知見においても、御指摘の「妊婦、胎児及び授乳中の乳児」に係る重大な懸念が報告されているものは承知していない。新型コロナ予防接種については、こうした審議会での専門家による議論等を踏まえ、妊娠中の者及び授乳中の者も対象として実施しているものである。
神谷宗幣(参政党)
ドイツのワクチン接種に関する常任委員会(STIKO)は、先日、「五十九歳までの健康な成人および妊娠中の女性には、通常、これ以上のブースターワクチン接種は推奨されない」と勧告した。政府は、この勧告の内容を把握しているか。
政府
お尋ねの勧告の内容については承知している。
神谷宗幣(参政党)
厚生労働省が令和五年三月十日に発出した「新型コロナワクチン(mRNAワクチン)注意が必要な誤情報」では、「ワクチン接種が流産の原因となる」という事項について「誤情報」と認定し、「ワクチンが胎児や生殖器に悪影響を及ぼすという報告はありません。妊娠中の方も、ワクチンを接種することができます。妊娠中の時期を問わず接種をおすすめします」との記載がある。ここでいう「ワクチンが胎児や生殖器に悪影響を及ぼすという報告」は、具体的にどの報告機関が政府のどの部署に報告するものを指すか。また、本件文書の記載を見れば、新型コロナワクチンが胎児に悪影響を及ぼす可能性が示唆されているところ、政府の言及するように、「ワクチン接種が流産の原因となる」ことが、明らかに「誤情報」であると断定できないように思われる。厚生労働省による令和五年三月十日発出の前記文書は撤回して見直すべきではないか。
政府
新型コロナワクチンの安全性や新型コロナ予防接種の実施に関する政府の考え方については、二についてで述べたとおりであり、御指摘のように「文書は撤回して見直すべき」又は「内容を再評価し、出し直すべき」とは考えていない。
神谷宗幣(参政党)
厚生労働省のウェブサイト「新型コロナワクチンQ&A」では、「ワクチン自体が母乳に移行する可能性は低く、万が一mRNAが母乳中に存在しても、子どもの体内で消化されることが予想され、影響を及ぼすことは考えにくいと報告されています」との記載がある。ここでいう報告とは、どの報告機関が政府のどの部署に報告するものを指すか。本件文書の記載を見れば、母乳を通じて、乳児にワクチン又はワクチンの成分であるスパイクタンパク質が影響を及ぼす可能性が示唆されており、前記Q&Aについては、内容を再評価し、出し直すべきではないか。
政府
お尋ねの「ワクチンが胎児や生殖器に悪影響を及ぼすという報告」及び「ワクチン自体が母乳に移行する可能性は低く、万が一mRNAが母乳中に存在しても、子どもの体内で消化されることが予想され、影響を及ぼすことは考えにくい」との「報告」については、特定の機関から政府に対して行われた報告を指しているものではなく、公表されている学術論文等から厚生労働省が収集した新型コロナワクチンの安全性等に係る知見である。新型コロナワクチンの安全性や新型コロナ予防接種の実施に関する政府の考え方については、二についてで述べたとおりであり、御指摘のように「文書は撤回して見直すべき」又は「内容を再評価し、出し直すべき」とは考えていない。
神谷宗幣(参政党)
現在、政府が把握している妊娠中及び授乳中のワクチンの曝露について、それぞれどのような副反応事例が何例あるか。授乳を介した曝露事例は何例あるか。
政府
お尋ねの「妊娠中」の「ワクチンの曝露について」「どのような副反応事例が何例あるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、妊娠中の者に対する新型コロナ予防接種に係る副反応疑い報告の件数を意味するのであれば、例えば、新型コロナ予防接種が開始された令和三年二月十七日から令和五年三月十二日までの間に製造販売業者から百十二例の副反応疑い報告があり、これらについて、「ICH国際医薬用語集日本語版」に基づく症状別に分類してお示しすると、「COVID―十九」が延べ十二件、「発熱」が延べ八件、「自然流産」が延べ七件、「腹痛」が延べ六件、「切迫早産」が延べ五件、「呼吸困難」が延べ五件、「倦怠感」が延べ五件、「出血」が延べ五件、「胎児死亡」が延べ五件等である。また、お尋ねの「授乳中」の「ワクチンの曝露について」「どのような副反応事例が何例あるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に、授乳中の者に対する新型コロナ予防接種に係る副反応疑い報告の件数を意味するのであれば、副反応疑い報告においては、被接種者が授乳をしているかどうかについて報告を求めておらず、網羅的に把握していないため、お答えすることは困難である。さらに、お尋ねの「授乳を介した曝露」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に「ICH国際医薬用語集日本語版」における「母乳を介した曝露」を意味するのであれば、同期間の製造販売業者からの副反応疑い報告において、「母乳を介した曝露」は三件報告されている。
神谷宗幣(参政党)
妊娠中は、普段より免疫力が低下していることから、BCGや、麻疹風疹ワクチンは接種できないこととなっている。この点、新型コロナワクチンは特例承認されたものであり、現在まで一部臨床試験中のワクチンである。政府は、どのような知見をもとに、妊娠中でも接種することが望ましいと判断したのか。また、妊婦や授乳中の乳児の安全性について、これまでどのような治験を行ってきたか。
政府
お尋ねの「妊婦や授乳中の乳児の安全性」については、令和三年二月十四日に承認を受けたファイザー社の新型コロナワクチンについて、当該承認の申請に当たって実施された臨床試験において妊娠中の者は対象から除外されていたものの、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の特例承認に係る報告書に記載のとおり、同社が収集した「海外における使用許可後又は製造販売後」の「自発報告」において、「妊婦」及び「授乳婦」に対する接種に関し、「妊婦は二十八例及び授乳婦は三十九例確認され」、それらについて、「妊婦二十八例のうち、二十六例で妊娠中のワクチン曝露が報告され、そのうち九例で臨床症状を伴う非重篤な事象(ワクチン接種部位疼痛四件、頭痛及び四肢疼痛各二件、血性分泌物、筋肉痛、疼痛及び鼻漏)が報告され」、また、「授乳中の乳児三十九例において、四例で非重篤の事象(腹部不快感、食欲減退、過敏症、疾患、乳児嘔吐、乳児易刺激性、不眠、易刺激性、嗜眠、発熱、発赤及び嘔吐各一件)が報告され」ており、これらも踏まえ、同機構は、「本剤の承認の可否に影響する重大な懸念は認められていない」との評価を行ったものであり、厚生労働大臣は、当該報告書を踏まえ、薬事・食品衛生審議会における議論を経て、承認を行ったものである。妊娠中の者への新型コロナ予防接種については、承認を受けた新型コロナワクチンについて、令和四年二月十日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において胎児への影響も含めた安全性等に関する知見等に基づき議論を行った上で、当該者への新型コロナ予防接種の実施が新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため必要であること、当該者への新型コロナ予防接種の有効性及び安全性に関する知見、諸外国における当該者への接種状況等を総合的に考慮し、当該者を対象として実施しているものである。なお、同社の新型コロナワクチンについては、承認後の医薬品安全性監視活動の一環として、妊娠中の者を対象とした臨床試験が海外で実施されていると承知している。
神谷宗幣(参政党)
過去、人口の半数を超える国民が、臨床試験中の新型コロナワクチンを短期間で複数回打ったという事象は、歴史的に存在しない。そうであるとすれば、新型コロナワクチンを接種した国民の生命、身体を守るために、新型コロナワクチンを推奨してきた政府が主導して接種者の健康状態に係るデータを取得し、長期的な検証を行う必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
政府
お尋ねの「長期的な検証」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナ予防接種を受けた者の健康状況については、現在、新型コロナワクチン接種後健康状況調査、令和二年度厚生労働行政推進調査事業費補助金新興・再興感染症及び予防接種政策推進事業による「新型コロナワクチンの投与開始初期の重点的調査(コホート調査)」、新型コロナワクチンについての承認を取得した製造販売業者が実施する医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十一号)第二条第一項に規定する製造販売後調査等に基づく報告等により、政府として情報収集に努めているところであり、政府としては、引き続き、専門家の意見も聴きながら、新型コロナ予防接種の安全性に係る情報の収集に努めるとともに、これらの情報等を踏まえ、必要な対応を行ってまいりたい。
質問1)mRNAワクチンの頻回接種による副反応の検証と評価
mRNAワクチンの副反応症状について審議会で専門家による議論が行われており、2023年3月10日時点で合同部会は「ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくこと」としている。
質問2)年一回の接種が必要であるとする医学的根拠
mRNAワクチンが全国民に「年一回」の接種が必要であるとする医学的根拠は具体的に上げられないが、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において決まったことである。
質問3)国内で希望する研究者へのワクチン提供
国内の研究者がmRNAワクチンを使用して実験できる仕組みはあるが、入手希望者一般に提供するつもりはなく、政府が認めたものにのみ提供している。
免疫学を専門とする東京理科大学村上康文名誉教授は、この点に関して、「mRNAワクチンには免疫抑制効果で日和見感染症を増加させる危険性に加え、頻回接種で自己免疫疾患発症のリスクが高くなること、接種するほど感染拡大を起こすこと」を指摘している。海外でも、免疫学の世界的権威であるフィラデルフィア病院小児ワクチンセンター長のPaul Allan Offit医師は、医学雑誌「The New England Journal of Medicine」誌においてオミクロン株対応二価ワクチンが既存の一価ワクチンより優れた免疫応答効果を示さないとの研究結果を基に、健康で若い人々に数か月後には消えてしまう変異株に対するmRNAを含むワクチンをブースター接種することで全ての症候的感染を防ごうとすることはやめるべきだと主張している。また、マサチューセッツ工科大学のRetsef Levi教授も、mRNAワクチンにより特に若い人々の間で深刻な被害が誘起されているとして接種中止を訴えている。
このことを裏付けるように、実際に国内においてワクチン接種が進んでも感染拡大は収まらず、健康被害の報告も増えている。政府の主張するワクチンの予防効果に疑問符がつく中、TBSテレビが行った二月の世論調査によれば、今後ワクチンを接種しないと答えた人が半数を超え、五類感染症への見直しに賛成する人が半数を超えている。国民のワクチンに対する信頼度は、現時点で高いものとは言えない。
以上を踏まえ、以下、質問する。
神谷宗幣(参政党)
mRNAワクチンの頻回接種による中長期的な副反応や副作用について政府はどのような検証を行い、どのような資料に基づき、どのように評価しているか。
政府
御指摘の「mRNAワクチンの頻回接種による中長期的な副反応や副作用」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)を受けたことによるものと疑われる症状については、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ予防接種に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の製造販売業者等から同大臣に報告されており、これらの制度により収集した情報等に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において、専門家による議論が行われ、新型コロナワクチンの安全性について評価を行っているところであり、令和五年三月十日の合同部会において、現時点では「ワクチンの接種体制に影響を与える重大な懸念は認められず、引き続き国内外の情報を収集しつつ、新型コロナワクチンの接種を継続していくこと」としてよいこととされている。なお、合同部会の資料については、厚生労働省のホームページで公表している。
神谷宗幣(参政党)
政府は、mRNAワクチンに関するどのような海外情報をどのようにして入手し、どのような方法で評価しているか。全ての国民に対して、「年一回」の接種が必要であるとする医学的根拠は何か。
政府
御指摘の「mRNAワクチン」を含め、新型コロナワクチンについては、公表されている学術論文等から、その有効性及び安全性に係る国内外の知見や諸外国の接種方針等について情報を収集し、これらの情報に基づき、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会(以下「分科会」という。)において、専門家による議論が行われ、重症化予防効果等について確認している。また、令和五年度の新型コロナ予防接種の方針については、令和五年三月七日の分科会において、「二千二十三年秋冬(九月~十二月)には接種可能な全ての者を対象に接種を実施」し、「令和四年秋開始接種から一年が経過する二千二十三年秋冬を待たずに、二千二十三年春から夏(五月~八月)と一定の時期を定めて、重症化リスクが高い者に接種を行うとともに、健常人であっても重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療機関や高齢者施設・障害者施設等の従事者に接種機会を確保する」ことが了承され、これを踏まえ決定したところ、当該方針については、同年二月八日に厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会で取りまとめられた「二千二十三年度以降の新型コロナワクチンの接種の方針について」で示されているとおり、新型コロナウイルス感染症の疫学的状況や新型コロナワクチンの有効性に関する疫学的知見等を踏まえ、秋から冬にかけて新型コロナ予防接種による有効性の発揮が必要であることや、接種後一年程度経過すると新型コロナ予防接種による有効性の十分な持続が見込めないものと考えられること等を根拠とするものである。
神谷宗幣(参政党)
mRNAワクチンは、研究途上段階である。他方、実際に同ワクチンを接種した国民から健康被害の報告が相次いでいるとの学会報告も増加しており、重大な薬害に至る可能性も否定できない。そうであれば、広く国内でも研究を進めるべきであり、国内の研究者がmRNAワクチンを使用して実験できるように、入手希望者にはワクチンを供給すべきと考えるが、政府の見解如何。
政府
御指摘の「mRNAワクチンは、研究途上段階である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「mRNAワクチン」を含め、新型コロナワクチンについては、医薬品医療機器等法による承認を受けたものについて、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号)による改正前の予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種に用いることを本来の目的として製造販売業者と供給契約を結んでいることから、政府が所有する新型コロナワクチンを御指摘の「入手希望者」一般に提供することは考えていない。ただし、国内における新型コロナワクチンの開発のために政府が費用を補助して研究を行う者に対しては、当該新型コロナワクチンの製造販売業者の同意を得た上で、例外的に提供している。
令和四年十一月二十五日に公表された人口動態統計速報によると、本年一月から九月の出生数の累計は五十九万九千六百三十六人であり、前年と比較してマイナス四・九パーセントとなっている。この数値は、調査開始以来、最も少なかった昨年の出生数を下回るものであり、松野官房長官は、十一月二十八日の定例記者会見において「危機的状況である」と述べた。
我が国において少子化問題は、喫緊の課題である。少子化の原因として、未婚化、晩婚化のほか、「夫婦の出生力の低下」が指摘されている(平成十六年版少子化社会白書)。
不妊の検査や治療を受けたことがある夫婦は、五・五組に一組に上り、現在、総出生数の七パーセント、およそ十四人に一人が生殖補助医療で誕生している。これまで不妊と言えば、女性側の問題として捉えられることが多かった。しかし近年、不妊原因の半数は男性側にあり、しかも男性不妊の原因の殆どが精子に何かしらの異常がある精子異常であると指摘されている。
平成三十年七月二十八日に放送された「NHKスペシャル ニッポン精子力クライシス」では、「今ニッポンの未来を脅かす、異常事態が男性の身体に起きている。精子の数が少ない、ほとんど動かないなど、受精して妊娠を成功させる精子の力「精子力」が、どんどん衰えている」というショッキングな内容を報じている。同番組によれば、欧米の男性の精子数は、ここ四十年で半減したという驚きの調査結果が出たという。そして、欧米よりもさらに心配なのが日本であり、精子数を欧州四か国と比べたところ、なんと最低レベルだったことが分かったとのことである。
不妊治療において、人工授精、体外受精、顕微授精の順に治療技術が高度化するが、中でも生殖補助医療の顕微授精は、頭部が楕円で元気に泳いでいる精子を正常と考え(運動精子=良好精子)、一つの運動精子を捕捉し、卵子に刺して人工的に授精を図る方法であり、精子の状態が悪い、精子数が少ない乏精子症や、精子運動率が低い精子無力症等の精子異常に対する最終手段として急速に普及した。顕微授精に必要な精子数は、たったの一つでよく、かつ人間の手により容易に受精率を上げられる技術であるという利便性から、適応範囲が大幅に広がり、現在では生殖補助医療の約八割を占めるに至っている。
不妊治療業界では、「運動精子が一つでもいれば妊娠できる」、「顕微授精が精子の問題を解決した」というイメージが定着している。しかし一方で、現場では顕微授精が不成功の場合、これ以上の治療法がないことから顕微授精を繰り返すしかなく、顕微授精反復不成功の事例が積み上がっている。このような夫婦は、治療を反復しているうちに妻の加齢による卵子の老化も加わり、二重苦になるという辛い現実があり、不妊治療を始めた夫婦の半数以上は妊娠に至らずに治療を終えるという実態がある。生殖補助医療の実施件数が年々増加傾向にあるにもかかわらず、冒頭で示したように総出生率が低下している事実は、現場の影の実態を裏付けている。
また、不妊治療業界では、長年にわたり「運動精子=良好精子」という認識の上に治療モデルが構成されてきた。そのため、多くの現場では、精子数、運動率、頭部形態等を主要な指標として精子側の妊孕力(女性を妊娠させる能力)を評価している。しかし、一見「元気よく泳ぐ良好精子」であっても、普通の顕微鏡では見えないDNA損傷等の精子異常が隠れている場合がある。大半の隠れ精子異常の背景には、「新生突然変異」という遺伝子の先天異常が関与し、通常の顕微鏡で判断できるような精子数の減少や運動率の低下という形では表れず、分子生物学的な特殊検査法でなければ見極めることができない。現実問題として、顕微授精反復不成功例の精子の中には、様々なタイプの隠れ精子異常が高頻度で見つかり、顕微授精反復不成功例の八割は精子異常が背景にあるとも言われる。
この点について、日本産婦人科学会も、「一般精液検査は、精液や精子の量的性状を示しているだけで、必ずしも精子の質的性状(受精能力)を直接、反映するものではない」と述べている(日本産科婦人科学会雑誌平成二十一年六十一巻六号)。すなわち、これまでの運動精子=良好精子とする治療モデルは精子の品質管理が不十分であり、運動精子を捕捉して刺すだけでは顕微授精の有効性、安全性を保証できないのである。顕微授精は、あくまでも精子の数の補足をする技術であり、遺伝子の問題が関わる精子異常を治療できる技術ではない。
現在、報告されている顕微授精による臨床統計(妊娠率)は、顕微授精を施行した夫婦の何割が妊娠したかをまとめたものに過ぎない。そのため、精子異常がない、もしくは、遺伝子の問題が関与しない軽度な精子異常のケースが妊娠率を押し上げているということになる。一方で、顕微授精が対応困難な重度な精子異常がある場合には妊娠率が極めて低くなるが、重症例の夫婦は「いつかは自分たちも妊娠できる」と期待して治療を続けて反復不成功例に陥るという図式がある。これが、顕微授精反復不成功例の八割は精子異常があるという背景につながっている。
つまり、顕微授精は、生まれつき精子の設計を支配する遺伝子に問題がある精子異常を治すことができる技術ではないことから、安全性と有効性の視点から言えば、「顕微授精は精子異常には不向きな治療法」ということとなる。
医療介入は必ずリスクを伴い、顕微授精だけが例外ではない。出生児の遺伝子の半分は精子が担うことから「どのような精子を穿刺するか」は出生児の健常性に直結する。前述したとおり、重度な異常精子を卵子に刺しても妊娠しないから反復不成功例が積み上がる訳だが、「命を造り出す」生殖補助医療において最も怖い点は、本来、受精しては困る、遺伝子の問題が関与している軽度から中等度の異常精子が顕微授精により人工的に授精させられ、妊娠、出産に至った場合に「どのような異常が生まれてくる子供に起きるのか」について未知の領域である点にある。我が国初の体外受精児が誕生して約四十年であり、生殖補助医療は新しい医療であるため、ヒトの平均寿命八十年以上の長期にわたり「安全である」ことを確認できた人はいまだいない。
一方、欧米では十年以上前から「顕微授精で生まれてくる子供に精神発達障害を含めた先天異常の発症率が高い」という報告もあり、アメリカ疾病対策予防センター(CDC)は「顕微授精と自閉症スペクトラム障害(社会性、コミュニケーション、行動面の困難を伴う発達障害の総称)との間に因果関係がないとは言い切れない」という見解を出している(※)。
(※)二〇一五年American Journal of Public Health
二〇一二年The New England Journal of Medicine
他方、日本の生殖補助医療による出生児の先天異常に関するフォロー体制においては、子供が成長している過程で診断が可能になる「自閉症スペクトラム障害」、「注意欠陥多動性症候群」、「精神発達遅滞」などの神経発達障害は含まれていない。
「顕微授精と自閉症スペクトラム障害を含む神経発達障害との間に因果関係がないと言い切れない」現状では、命を造り出す生殖補助医療においては、因果関係があるという前提で危機管理をすべきである。特に、顕微授精に用いる一つの精子の選定は「命の選択」になる可能性を否定できないから、尚のことである。
以上を踏まえ、現行の顕微授精に代表される生殖補助医療に関し、以下、質問する。
神谷宗幣(参政党)
現在、日本生殖医学会において生殖医療専門医として認定を受けている九百七十三人のうち、主に男性側を診る泌尿器科医師数は僅か七十一人である。中でも、臨床精子学(ヒト精子の基礎研究)を専攻して博士論文を取得し、長年にわたり「ヒト精子」に精通し、臨床(患者)に橋渡しをしている医師は極めて少ない。専門医を増やす必要があると考えるが、政府は、どのような方策をとろうとしているのか。
政府
一般に、専門医の認定については、専門家による自律性を基盤として、各学会や一般社団法人日本専門医機構により行われているものである。御指摘の「生殖医療専門医」については、一般社団法人日本生殖医学会において、所定の研修を修了した産婦人科専門医又は泌尿器科専門医について研修及び認定を行っているものと承知しており、現時点において、政府として、「生殖医療専門医」を「増やす」「方策」については検討していない。
神谷宗幣(参政党)
ヒト精子の基礎研究に取り組む専門医が極めて少ないという背景も相まって、顕微授精は「一つの運動精子がいれば妊娠できる」というイメージが定着し、この約四十年、精子側の正確な科学的根拠に基づく医療(EBM。Evidence-Based Medicineの略)の提供がないまま、「運動精子=良好精子」とする治療モデルが生殖補助医療の八割を占めるまで普及した側面があると思われる。顕微授精の設計(精度)管理上、精子側の情報が不十分なまま技術提供したことが、治療の有効性と安全性を損なってきた可能性がある。精子の質を適切に管理することが生殖補助医療の効果を高め、リスクを軽減する取組の一つと考えられる。政府としては、ヒト精子の研究水準を高めるための方策をどのように考えているか、示されたい。
政府
お尋ねの「ヒト精子の研究水準を高める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国立研究開発法人日本医療研究開発機構が実施している成育疾患克服等総合研究事業において、「精子の「質」の評価方法」に関する研究を含め、「ヒト精子」に係る研究が行われてきているところである。
神谷宗幣(参政党)
令和四年四月から不妊治療が保険適用されたことにより、一般の疾病と同様、生殖補助医療も有効性と安全性が認められた標準治療であることが前提条件となった。科学的根拠に基づいた医療の提供と、医療経済の観点から、不妊治療の適正化、効率化つまり費用対治療効果が求められる。結果として保険適用化に伴い、今まで議論されなかった「精度の高い臨床統計」に基づいて、「顕微授精の安全性、有効性」を明確にしなくてはならない。そのためにも、精子側の正確な科学的根拠に基づいた医療による「治療の限界」の提示と、リスクを含む適応基準の明確化(治療内容の絞り込み)が急務である。同時に、保険適用に伴い、「施設における技術格差がない」医療行為・措置の均質化が求められてくるため、施設ごとの実態調査をする必要性も生じる。これらに関し、政府としては、どのような方法で「治療の限界」の提示とリスクを含む適応基準の明確化、現場の実態調査を行う見通しであるかについて見解を示されたい。
政府
三及び五について
お尋ねの「「治療の限界」の提示とリスクを含む適応基準の明確化、現場の実態調査」及び「保険診療下で出生児に何らかの問題が認められた場合には、医療機関に限らず、政府も責任を負う可能性が生じることになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、顕微授精を含む不妊治療については、令和三年度に厚生労働科学研究費補助金による「生殖医療ガイドラインの適切な運用と今後の改良に向けた研究」において関係学会により作成された「生殖医療ガイドライン」で示された有効性、安全性等を踏まえて、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)において検討が行われた結果、保険適用の対象としたところであり、例えば、令和四年度診療報酬改定において、男性不妊治療に関し「Y染色体微小欠失検査」を保険適用の対象としているところである。この不妊治療の保険適用に際しては、不妊治療を実施する医療機関の診療報酬上の施設基準を定めるとともに、前年度における実施件数や安全管理に係る事項等について医療機関に対して報告を求めることとしている。また、今後についても、令和四年二月九日の中医協の答申の附帯意見において、「不妊治療について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、・・・学会等における対象家族・年齢、治療方法、保険適用回数、情報提供等に関する検討状況を迅速に把握しつつ、適切な評価・・・等について検討すること」とされていることも踏まえ、政府としては、不妊治療に係る科学的知見の収集等について適切に対応することとしている。
神谷宗幣(参政党)
現行の生殖補助医療では、精子側の正確な科学的根拠に基づいた医療の提供がないまま、採卵を繰り返す治療モデルが画一化され、その治療法に対して保険適応がされている。しかし、「不妊である」ことはあくまでも結果であり、不妊になる原因や背景は夫婦ごとに大きく異なる。このように、「不妊治療は究極の個別医療」であり、一律に同じ治療(画一化治療)をすることは低効率である。保険診療は標準治療であることが前提になるが、不妊治療はそもそも標準治療になじまない。にもかかわらず、現状のままでは、採卵を繰り返して顕微授精を反復することにより、国家財政が厳しくなる可能性も否定できない。また、一律保険点数内で管理された技術提供に収めざるを得ない状況になることにより、医療の質が低下する可能性や二次的な社会問題が発生するリスクも否定できない。政府は、このリスクについてどのような検討を行っているか、見解を示されたい。
政府
お尋ねの「リスク」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、三及び五についてでお答えしたとおり、不妊治療については、「生殖医療ガイドライン」を踏まえて、中医協において検討が行われた結果、保険適用の対象としている。また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和四年三月四日付け保医発○三○四第一号厚生労働省保険局医療課長及び歯科医療管理官連名通知)により、医療機関は、不妊治療の実施に際して、患者等の状況に応じて治療計画を作成することとしており、当該治療計画についても、少なくとも六月に一回以上、必要に応じて見直しを行うこととしている。
神谷宗幣(参政党)
命を造り出すことになる生殖補助医療では、何より安全が最優先されなくてはならない。だからこそ、精子側の正確な科学的根拠に基づいた医療の提供がなく、運動精子一つを卵子に刺す顕微授精で生まれてくる子供の異常との因果関係を完全に否定できない現状において、保険診療下で出生児に何らかの問題が認められた場合には、医療機関に限らず、政府も責任を負う可能性が生じることになる。この問題をどう考えるか、政府の見解を示されたい。
政府
三及び五について
お尋ねの「「治療の限界」の提示とリスクを含む適応基準の明確化、現場の実態調査」及び「保険診療下で出生児に何らかの問題が認められた場合には、医療機関に限らず、政府も責任を負う可能性が生じることになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、顕微授精を含む不妊治療については、令和三年度に厚生労働科学研究費補助金による「生殖医療ガイドラインの適切な運用と今後の改良に向けた研究」において関係学会により作成された「生殖医療ガイドライン」で示された有効性、安全性等を踏まえて、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)において検討が行われた結果、保険適用の対象としたところであり、例えば、令和四年度診療報酬改定において、男性不妊治療に関し「Y染色体微小欠失検査」を保険適用の対象としているところである。この不妊治療の保険適用に際しては、不妊治療を実施する医療機関の診療報酬上の施設基準を定めるとともに、前年度における実施件数や安全管理に係る事項等について医療機関に対して報告を求めることとしている。また、今後についても、令和四年二月九日の中医協の答申の附帯意見において、「不妊治療について、今回改定による影響の調査・検証を行うとともに、・・・学会等における対象家族・年齢、治療方法、保険適用回数、情報提供等に関する検討状況を迅速に把握しつつ、適切な評価・・・等について検討すること」とされていることも踏まえ、政府としては、不妊治療に係る科学的知見の収集等について適切に対応することとしている。
神谷宗幣(参政党)
不妊治療の保険適用がこれまでの生殖補助医療の過去を総括して見直す良い機会になり、安全性戦略に向けたガイドライン等が策定されることが期待される。同時に、生殖補助医療に携わる現役医師の臨床精子学の教育研修(知識・技術・経験)強化が早急に求められる。政府の見解を示されたい。
政府
お尋ねの「安全性戦略に向けたガイドライン等」及び「臨床精子学の教育研修(知識・技術・経験)強化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「生殖医療ガイドライン」の中で、科学的根拠並びに国内の検査及び治療の実態に基づいて、生殖医療の標準的な検査及び治療について示されたところである。
質問1)G20におけるワクチン接種証明書の議論
G20バリ首脳宣言において、ワクチン接種証明書について議論がなされたが、詳細を示すつもりはない。
質問2)WHO規格を用いたデジタル証明書
インドネシア保健大臣が「WHO規格を用いたデジタル証明書」と発言したことを、政府は承知しておらず、確認するつもりもない。
質問3)ワクチン接種証明書と個人の選択の自由
ワクチンの接種を受けていないことを理由とした不当な差別的取扱いが行われることがないよう、厚生労働省においてリーフレット等を作成し、同省のウェブサイトに掲載すること等により周知を行っている。
また、これに先立つG20ビジネスサミットでは、インドネシア保健大臣ブディ・グナディ・サディキン氏が「ワクチンや検査を適切に受けていれば、移動は可能だ」、「G20各国は、このWHO規格を用いたデジタル証明書に合意した。我々は、国際保健規則の改正として、これを次のジュネーブでの世界保健総会に提出する」と発言するなど、G20の合意で、ワクチン接種証明書を移動のための国際規格にしようとの動きもみられている。
ワクチン接種証明書は、その運用をめぐり専門家も含めて多くの反対意見が出されている議論の余地のある重要な問題である。政府は、このような重大な問題については、不安を抱いている国民にしっかり説明すべきと考える。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類は、致死率の高いエボラ出血熱のような極めて危険な疾病と同じ二類相当に位置付けられたままであるが、それに相当する危険性を示すような致死率等、客観的なデータは見当たらない。それにもかかわらず、いまだに新型コロナウイルスワクチンを全ての国民に何度も何度も接種させようとする政府に対して、多くの国民がますます強い不安と疑念を感じている。深刻な副反応被害についても被害者団体が結成され、多くの専門家が警鐘を鳴らし、大手メディアもその被害実態を報じ始めている。
そうした中で、G20において、ワクチン接種証明書の普及を促すような宣言が採択されたことで、多くの人が今後、如何なるワクチンであっても政府が一旦推奨すれば、社会生活の条件として接種を強制されるのではないかと危惧している。
そこで以下、質問する。
神谷宗幣(参政党)
G20バリ首脳宣言において、ワクチン接種証明書について、どのような議論がなされたのか。議論の詳細を示されたい。また、ワクチン接種証明書について何がどのように合意されたのか、合意内容の詳細を示されたい。
政府
お尋ねの点も含め、本年十一月に開催されたG20バリ・サミットにおける議論の詳細については、今後のG20における議論に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。また、お尋ねの「ワクチン接種証明書について何がどのように合意された」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同サミットにおける合意内容については、G20バリ首脳宣言に記載されているとおりである。
神谷宗幣(参政党)
インドネシア保健大臣の発言にある「WHO規格を用いたデジタル証明書」とは具体的には何か。今後、海外渡航の際に取得を義務付けられるおそれのあるものなのか。その方針、具体的内容を示されたい。
政府
御指摘の「インドネシア保健大臣の発言」について政府として承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
神谷宗幣(参政党)
政府として、今後のワクチン接種証明書の運用について、どのように考えているのか。ワクチン接種証明書が個人の選択の自由を阻害しないために、どのような具体的な措置を採るのか明らかにされたい。
政府
お尋ねの「今後のワクチン接種証明書の運用」及び御指摘の「ワクチン接種証明書が個人の選択の自由を阻害しない」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、ワクチンの接種を受けていないことを理由とした不当な差別的取扱いが行われることがないよう、厚生労働省においてリーフレット等を作成し、同省のウェブサイトに掲載すること等により周知を行っている。
質問1)「ワクチンがもたらす感染拡大防止効果」の根拠
ワクチンを接種すればウイルスを他の人への感染を防止できるかどうかについて、ファイザー社はテストを行っておらず、政府も行うつもりはない。ワクチンの感染予防効果は、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会の議論を根拠としている。
質問2)ワクチン購入量
重症化率がデルタ株以前と比べて大きく低下しているにも関わらず、令和四年三月の予備費で、ワクチン接種1億7300万回分を確保した。
質問3)製薬会社との秘密保持契約
製薬企業は情報開示により不利益を被る恐れを理解しており、日本政府は契約締結のために秘密保持契約を締結し、企業に不利益を与えない範囲内において情報開示に努めてきた。
質問4)秘密保持契約の解除
秘密保持契約の解除を企業側と協議を進めているかについて、政府からの回答はない。
質問5)裁判への証拠提供と秘密保持契約
新型コロナワクチンの接種後死亡事例の裁判において証拠請求がなされた場合に、証拠提供が秘密保持契約に優先するのか、という点について回答するつもりはない。
この数量は、我が国の二〇二二年一月現在の総人口一億二千三百二十二万三千五百六十一人が七回以上接種しても余るほどであり、各国におけるパンデミック対応の収束状況を鑑みればあまりに過大なストック状況といわなくてはならない。
この点について財務省は、「結果として総人口×接種回数を大きく上回る数量の購入となっているが、ワクチンがもたらす感染拡大防止の効果ひいては経済的な効果も踏まえたうえで、費用対効果を考えるべき」としながら、「今後とも、ワクチンが必要となる時期や変異株への対応などを可能な限り見込みながら適切な調達に努めること」としている(令和四年四月十三日開催財政制度等審議会財政制度分科会財務省作成資料)。
このワクチン確保のみに国家予算の二%を上回る膨大な予算が割かれているという異常に見える措置の政策意図や合理的説明について、政府はワクチン提供企業と秘密保持契約を締結していることを理由に明らかにしていない。
日本貿易振興機構(JETRO)ウェブサイトに掲載された「ビジネス短信」二〇二一年一月十九日付記事「新型コロナワクチン接種で先行のイスラエル、ファイザーとの契約書を公開」において、イスラエルでは、昨年、ワクチン供給と引き換えに被接種者の医療情報をファイザーなどのワクチン供給元に提供すると現地紙が報じたことをきっかけに、同国政府が透明性を担保するためとして、ファイザーとの間で締結された契約書を公開したことが報じられている。
また、欧州議会議員Rob Roos氏は、二〇二二年十月十一日に自身のTwitterにおいて、「COVID公聴会でファイザー社のディレクターは、ワクチンについて感染防止効果のテストはしていないことを認めた。「他者に対する感染を防止するために予防接種を受ける」という呼び掛けは、全くの嘘」であり、「COVIDパスポートの唯一の目的は人々にワクチン接種を強制することである」と述べている。
以上の情報に鑑みるなら、全国民が七回以上接種してもなお、余る量のコロナワクチンを政府が確保した意図に大きな疑念を持たざるを得ない。
そこで、以下質問する。
神谷宗幣(参政党)
欧州議会のCOVID公聴会でファイザー社役員が「ワクチンを接種すればウイルスを他の人への感染を防止できるかどうかについては、テストを行っていない」と述べたとされていることについて、政府は状況を調査したか。政府のいう「ワクチンがもたらす感染拡大防止の効果」とはどのような根拠に基づくものか。
政府
お尋ねの「欧州議会のCOVID公聴会でファイザー社役員が「ワクチンを接種すればウイルスを他の人への感染を防止できるかどうかについては、テストを行っていない」と述べたとされていること」については、直接的な「状況」の「調査」を行っていないが、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)については、ファイザー社の新型コロナワクチンも含め、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会において、企業から提供されるデータや海外の論文等の科学的知見等に基づき、専門家による議論が行われ、発症予防効果、重症化予防効果等について確認している。
神谷宗幣(参政党)
令和四年三月の予備費においても、ワクチン接種一億七千三百万回分が確保されている。すでに新型コロナウイルスの流行は、重症化率がデルタ株以前と比べて大きく低下しているオミクロン株に置き換わっている現状において、これほど多くの新型コロナワクチンを確保する必要性はないのではないか。あわせて、今後のワクチン確保について、いつまで、どのような規模で継続させるのか、あるいは継続させないのか、理由を含めた政府の考えを示されたい。
政府
令和四年度予備費を使用して購入した新型コロナワクチンのうち、ファイザー社の新型コロナワクチン千万回分及びモデルナ社の新型コロナワクチン千八百万回分は、新型コロナ予防接種における三回目の接種の促進のために必要であったことから購入したものである。また、令和四年度予備費を使用して購入した新型コロナワクチンのうち、ファイザー社の新型コロナワクチン七千五百万回分及びモデルナ社の新型コロナワクチン七千万回分は、新型コロナ予防接種を追加的に実施する可能性に備え、どの企業がオミクロン株に対応する新型コロナワクチンの開発に成功するのか明らかではない中で、実施に必要な数量を確実に確保する必要があったことから購入したものである。また、令和五年度以降の新型コロナ予防接種の在り方については、今後の感染状況等を踏まえ、適時適切に判断していくこととしており、仮に実施することとなった場合の枠組み等は現時点で決まっていないが、様々な可能性を考慮し、事前に一定数量の新型コロナワクチンを確保しておく必要があると考えている。
神谷宗幣(参政党)
令和四年四月十八日の衆議院決算行政監視委員会において、後藤茂之厚生労働大臣(当時)は、「交渉中や契約締結後も含め、交渉や契約に関する情報が公になった場合は、企業側が他国と交渉する際に不利益を被るおそれがあり、その結果、我が国とは契約を結ばないという事態になることを避けるために、企業と秘密保持契約を締結している」と答弁している。そうであるとすれば、企業側が他国と交渉する際に不利益を被るおそれがない事項については、可能な限り国民に明らかにすべきではないか。また、同秘密保持契約の内容を岸田文雄総理大臣は承知しているのか。
政府
お尋ねの「不利益を被るおそれがない事項」及び「協議」の意味するところが必ずしも明らかではないが、新型コロナワクチンに係る企業との交渉や契約に関する情報の公開については、これまでも可能な限りの対応に努めてきたところであり、引き続き、「秘密保持契約」を踏まえ、適切に対応してまいりたい。また、「秘密保持契約」は各企業と政府との間で締結しており、その内容については、政府として承知しているものである。
神谷宗幣(参政党)
前記三で取り上げた答弁において後藤大臣は、「将来的にどの範囲の情報を公表することができるかにつきましては、引き続き、企業との間でコミュニケーションを重ね、可能な限りの情報公開に努めてまいりたい」と答弁しているが、これは、秘密保持契約の解除を含めて、現在企業側と協議を進めているということか。
政府
回答なし
神谷宗幣(参政党)
今後、新型コロナワクチンの接種後死亡事例等に関し、訴訟等が提起される可能性がある。法廷における審理で証拠請求があった場合等、秘密保持契約の制約にもかかわらず同契約の内容は証拠提供されるのは当然と考えるが、政府としてどう判断するか。
政府
お尋ねについては、仮定の御質問であり、お答えすることは差し控えたい。
質問1)治療を受けられないワクチン副反応患者
ワクチン接種後に患者が身体の不調を訴えても治療を受けられないケースは多数あるが、政府としては、合同部会で専門家の評価を受けたうえでホームページでの情報公開、都道府県に相談窓口の設置や医療体制の確保を依頼しており、治療を受けられないケースがあると承知していない。
質問2)ファイザー社への治験データの開示要求
2022年3月1日にファイザー社からFDAへ提出されたデータファイルには、1291種類の副反応が報告されているが、政府としてはファイザー社に治験データの開示を求める必要はなく、ファイザー社がコミナティ筋注の特例申請を行った際のデータで十分であると認識している。
質問3)新型コロナワクチンによる月経異常
月経異常に関して以下が報告されている。①医師からの報告:月経障害3件、月経遅延1件、重度月経出血3件、不規則月経四件及び無月経1件 ②製造販売業者からの報告:希発 月経1件、月経困難症12件、月経障害8件、月経遅延2件、月経中間期出血24件、月経不快感1件、重度月経出血12件、頻発月経3件、不規則月経6件及び無月経1件
質問4)子供のワクチン接種
子供のワクチン接種は、厚生科学審議会の議論により決定している。
しかし、これまでの接種推進の中で、副反応の発生が見られるほか、子供たちへの「接種機会提供」と称してのワクチン接種促進の動きが保護者の不安を招いている。
そこで以下質問する。
神谷宗幣(参政党)
令和四年七月八日に開催された、第八十一回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和四年度第六回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(合同開催)において、「副反応疑い報告状況」として帯状疱疹、肝機能障害から呼吸困難に至るまで、多くの症例が報告されている。しかし、医療現場においてこれら副反応に関わる様々な症例の報告が十分に周知されておらず、患者側が接種後の身体の不調を訴えても、治療を受けられないケースが多数あるとの声が寄せられている。この状況に鑑み、政府は、前記部会において報告されている「副反応疑い報告状況」について、医療機関に積極的に十分な情報を開示し、治療に結びつけるための対策を講ずるべきではないか。政府の見解を示されたい。
政府
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「新型コロナ予防接種」という。)を受けたことによるものと疑われる症状については、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項の規定により、医師等から厚生労働大臣に報告されているほか、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第六十八条の十第一項及び第二項の規定により、新型コロナ予防接種に使用するワクチン(以下「新型コロナワクチン」という。)の製造販売業者等から同大臣に報告されており、これらの制度により情報収集を行っている。また、予防接種法第十二条第一項及び第十四条第一項並びに医薬品医療機器等法第六十八条の十第一項及び第二項並びに第六十八条の十三第一項の規定に基づき、新型コロナ予防接種に関し、医師、製造販売業者等から報告され、独立行政法人医薬品医療機器総合機構において情報を整理し、調査が行われた全ての事例については、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(以下「合同部会」という。)において専門家の評価を受けた上で、定期的に厚生労働省ホームページで公表することとしている。さらに、御指摘の「治療に結びつけるための対策」の具体的に意味する範囲が必ずしも明らかではないが、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、「新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応を疑う症状に対する診療体制の構築について」(令和三年二月一日付け健健発〇二〇一第二号厚生労働省健康局健康課長通知。以下「課長通知」という。)を発出し、都道府県に対し、当該症状に対応する相談窓口の設置や医療体制の確保を依頼したところであり、全ての都道府県において相談窓口が設置され医療提供体制が構築されているものと承知している。
神谷宗幣(参政党)
令和四年三月一日、米国食品医薬品局(以下「FDA」という。)が米国の裁判所の命令に基づき、ファイザー社からFDAへ提出された同社の新型コロナワクチンに係るデータファイルの一部を開示している。この点、開示されたデータの中には、使用許可後の累積報告データとして、腎臓障害、急性弛緩性脊髄炎、脳幹塞栓症、心停止、出血性脳炎など実に千二百九十一種類の副反応が報告されている。この報告につき、政府は、同社の作成したデータの真偽については答える立場にないとの答弁を行っているが、多くの国民が同社製ワクチンを接種していることに鑑み、同社に治験データの開示を求めるとともに副反応についてあらゆる症例の調査を実施し、内容をすみやかに開示すべきではないか。政府の見解を示されたい。
政府
御指摘の「同社に治験データの開示を求める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねに関し、ファイザー社のコミナティ筋注の特例承認の申請に当たっては、有効性及び安全性に関し必要なデータが厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して提出されており、また、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、御指摘の同社の海外における情報も含め、同省及び同機構において新型コロナワクチンにおける必要な情報の収集及び調査を行い、定期的に開催している合同部会において提供し、専門家の評価を受けた上で、定期的に同省ホームページで公表することとしている。
神谷宗幣(参政党)
副反応の目立つ事例として、女性の月経異常の可能性が指摘されている。米国で行われた新型コロナワクチン接種と月経異常に関する約三万九千人を対象とした調査において、ワクチン接種後に四十二%で月経量が増加、さらに閉経者の六十六%で不正性器出血が報告されているほか、英国の調査でも接種後の月経異常に関連する報告が六万件以上あるとの報告がある。わが国では、「副反応疑い事例の報告状況」に挙がっている月経異常に関する報告の数は僅かであるが、一方、一般社団法人こどもコロナプラットフォームが、十二歳から五十七歳までの九十五名に実施したアンケート結果によると、新型コロナワクチン接種前に月経異常が見られなかった人が八割であるのに対し、七割の人が新型コロナワクチン接種後の月経異常を感じていたという結果が得られた。こちらのデータを見るなら、新型コロナウイルスワクチン接種と月経異常との間の関連性が疑われる。こうしたこともあってか、令和四年七月十二日、国立研究開発法人国立成育医療研究センターと株式会社エムティーアイが、新型コロナウイルスワクチン接種と月経異常との疫学的関連性についての調査を開始すると発表した。月経異常は、女性の出産にも影響する深刻な問題である。上記のような現状を政府はどう考えるか。何らかの対策を検討しているか。
政府
御指摘の「月経異常」の意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に月経に係る副反応を意味するものであるとすれば、これを含め、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、厚生労働省及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構において新型コロナワクチンにおける必要な情報の収集及び調査を行い、定期的に開催している合同部会において提供し、専門家の評価を受けた上で、定期的に同省ホームページで公表することとしている。具体的には、令和四年八月五日の合同部会において、新型コロナワクチンのうちコミナティ筋注に関しては、医師等からは、月経障害三件、月経遅延二件、重度月経出血三件、不規則月経四件及び無月経一件が報告されており、製造販売業者からは、希発月経一件、月経困難症十二件、月経障害八件、月経遅延二件、月経中間期出血二十四件、月経不快感一件、重度月経出血十二件、頻発月経三件、不規則月経六件及び無月経一件が報告されている。また、新型コロナワクチンのうちスパイクバックス筋注に関しては、医師等からは、月経困難症一件及び月経中間期出血一件が報告されており、製造販売業者からは、月経中間期出血二件及び重度月経出血二件が報告されている。なお、これらは重複して報告される場合がある。また、新型コロナ予防接種を受けたことによるものと疑われる症状については、一についてで述べたとおり、課長通知を発出し、都道府県に対し、当該症状に対応する相談窓口の設置や医療体制の確保を依頼したところであり、全ての都道府県において相談窓口が設置され医療提供体制が構築されているものと承知している。
神谷宗幣(参政党)
新型コロナワクチンには中長期にわたる治験や運用に基づく安全性データがないことから、日本の未来を託す子供に接種することについて、より慎重に判断すべきである。政府は、子供へのコロナウイルスワクチン接種について、五歳から十一歳の接種は、「努力義務としない」としているが、実施している自治体によっては、「強制ではないが、多くの人に接種を検討してほしい」と呼び掛けたり、接種券を子供にも一律に発送したりしているところもある。こうした動向の中で、子供の接種について安全性に関わる情報が不十分なままに、判断を下さねばならなくなった保護者から困惑の声が寄せられている。政府のいう子供の接種について「努力義務としない」とは、「接種の機会を提供する施策の推進であり、接種はあくまで受ける当事者、保護者の判断で決めるもの」と理解してよいか、また、リスクとベネフィットを比較衡量すれば子供の接種そのものについて慎重に考えるべきであることについてどう考えるか、政府の見解を明確に示されたい。
政府
「努力義務」に関するお尋ねについて、予防接種法第九条(同法附則第七条第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定は疾病のまん延を予防するために可能な限り接種を受けていただきたいという趣旨に基づく努力義務を定めるものであり、対象者又はその保護者が同法に基づく予防接種を受けるか否かを判断するものである。また、五歳から十一歳までの者への同法附則第七条第一項の規定による新型コロナ予防接種は、医薬品医療機器等法による承認を受けた新型コロナワクチンについて厚生科学審議会において有効性及び安全性に関する議論を行った上で、当該者への新型コロナ予防接種の実施が新型コロナウイルス感染症のまん延予防のため必要であること、当該者への新型コロナ予防接種の有効性及び安全性に関する知見、諸外国における年少者への接種状況等を総合的に考慮し、当該者を対象として実施しているものである。
質問1)新型コロナウイルス感染症対策の基本基本的対処方針
厚生労働省事務連絡では「マスク着用を推奨する」一方で、基本的対処方針では「マスクの着用を徹底する」とされているが、これは徹底を促すとの趣旨であり、政府は改定の必要がないと考えている。
質問2)本人の意に反してマスクの着脱を無理強いする事例
厚生労働省ホームページの「新型コロナウイ ルスに関するQ&A(一般の方向け)」に記載している。
質問3)「マスク着用は任意によるもの」の周知施策
政府としては、本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないように、テレビコマーシャル、SNS、インターネッ ト広告、リーフレット等を活用して、周知していくつもりである。
質問4)2メートル以下ならマスク推奨とする根拠
2022年3月28日に公表した「新型コロナウイルス(SARS|Covid)の感染経路について」において、「感染者との距離が近いほど(概ね一―二メートル以内)感染する可能性が高く、距離が遠いほど(概ね二メートル以上)感染する可能性は低くなる」とするものであり、国立感染症研究所が世界保健機関と米国疾病予防管理センターの知見を踏まえて作成している。
欧米諸国では既にマスク着用を対策から外しているところがほとんどである。欧米でマスクを着用しなくなったのは、現在流行しているオミクロン株の病態自体が、昨年のデルタ株以前の新型コロナウイルスからの変異によって、喉の粘膜で感染する、私たちが子どもの頃から罹ってきたのとほぼ同じ喉風邪へと変化したため、重症化率が大きく低下したことが大きい。
マスクそのものが元々健全なエネルギー代謝やコミュニケーションを抑制して心身の健康を害するリスクが高いことにも鑑みれば、政府は新型コロナ対策としてマスク着用を推奨することをやめ、自由化すべきであるというのが参政党の立場である。今回の岸田総理の発言は、そうした方向に進もうという前向きな姿勢を示したものと受け止めている。
既に厚生労働省ウェブサイト上で、感染対策としてのマスク着用については「場面に応じた適切なマスクの着脱をお願いします」として、「屋外では季節を問わず、マスクの着用は原則不要です。」、「屋内では距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合をのぞき、マスクの着用をお願いします。」と例示している。また、子供以外のマスク着用について、屋外では、「マスク着用を推奨 他者との身体的距離(二m以上を目安)が確保できない中で会話を行う場合のみです。」、「それ以外の場面については、マスクの着用は必要ありません。(中略)特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。」と例示している。
これらを見る限り、我が国においても屋外では原則マスク着用は不要と政府が認識しているのは明らかであるにもかかわらず、ほとんどの人がマスクを着用して屋外歩行している光景が一般的である。
我が国でこのような状態が継続されているのは、政府が「マスクは屋外では原則として不要」としているにもかかわらず、その周知について曖昧さを多く残しているためと言わざるを得ない。「マスクは屋外で原則不要」という指針が普及しないのは、そもそも政府が事務連絡等で示している「マスク着用」又は「マスク不着用」の任意性に関して理解の混乱があることを指摘したい。
例えば、厚生労働省事務連絡「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱いについて」(令和四年五月二十日付)によると、屋外でのマスク着用、屋内でのマスク着用については、感染リスクがある場合について、マスク着用を「推奨する」としている。
また、厚生労働省事務連絡「マスクの着用に関するリーフレットについて(周知)」(令和四年五月二十五日付)では、「周知に当たっては、本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないよう、丁寧な周知をお願い申し上げます」としている。
つまり、政府見解では「感染リスクがある場合においても、マスク着用は推奨されるものであり、本人の意に反してマスクの着脱を無理強いしてはならない」ものといえる。
一方、内閣総理大臣を本部長とする新型コロナウイルス感染症対策本部の決定「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)(令和三年十一月十九日(令和四年九月八日変更))によると、「(4)感染防止策」においては、感染リスクがある場合は、マスクの着用を推奨するとしているが、「(5)オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策」の「1)国民への周知等」の項では、「会話をする際にはマスクの着用を徹底すること」、「2)学校等」の項では、「部活動前後の集団での飲食の場面や移動に当たっては、マスクの着用を含めた感染対策を徹底する」としている。
この点について、「推奨」とは、国語辞典によると「人・事物などのすぐれていることをあげて、それを人にすすめること」とされており、相手側は任意で応じるものと解する。一方、「徹底」とは、「態度・行動が中途半端でなく、一つの考え方で貫かれていること。」、「命令・方針などがすみずみまで行き渡ること。」とされており、相手側に行為を強制するものと解する。
この二つの用語は任意性と強制性において意味が全く異なっている。各都道府県や市町村の健康担当部局では、新型コロナウイルス感染症対策については基本的対処方針を基準に感染症対策を推進しているところ、この「推奨」と「徹底」の混在により、「マスク着用」の考え方について大きな混乱が生じており、それが日本社会の「脱マスク化」を妨げる一つの要因となっている。こうした混乱を招く表現はすぐに改められるべきであるし、基本的対処方針全体を再検討すべきと考える。
そこで、以下質問する。
神谷宗幣(参政党)
厚生労働省事務連絡等で示された、感染リスクのある場所における「マスクの着用を推奨する」の意味は、マスク着用は任意によるべきで、誰からも決して強制されるものではないということであるか。そうであれば基本的対処方針の「マスクの着用を徹底する」は誤解を与えているので「推奨する」等、任意性を明確にしたものに訂正するべきではないか。
政府
お尋ねの「マスクの着用を推奨する」との記載は、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、マスクの着用は重要であるため、会話を行う際等にマスクを着用する等、国民に対して、場面に応じた適切なマスクの着脱を勧めるという意味である。また、御指摘の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定、令和四年九月八日変更。以下「基本的対処方針」という。)の記載は、「会話をする際にはマスクの着用を徹底すること」を「促す」としているとおり、国民に対して、場面に応じた適切なマスクの着脱を勧めるものであり、「マスクの着用を推奨する」と同様の趣旨であるため、御指摘のように「誤解を与え」るものではなく、「訂正する」必要があるとは考えていない。
神谷宗幣(参政党)
厚生労働省事務連絡(令和四年五月二十五日付)でいう「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いする」事例がいまだに日々の生活の中で頻発しているが、この具体的ケースとしてどのようなものが挙げられるか、例示されたい。
政府
御指摘の「「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いする」事例がいまだに日々の生活の中で頻発している」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の事務連絡における「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすること」については、例えば、厚生労働省のホームページの「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」(以下「厚生労働省のホームページのQ&A」という。)に掲載しているとおり、「正しくぴったりとマスクを着用することは難しい」就学前の子どもに対して、「子どもや保護者の意図に反してマスクの着用を実質的に無理強いする」ことが挙げられる。
神谷宗幣(参政党)
「マスク着用は任意によるもの」との理解を一層、広めていくために、テレビコマーシャルやインターネット上の広告を利用し、より強力、効果的な広報を展開していくべきと考えるが、政府の見解如何。
政府
政府としては、こうしたマスクの着用の考え方について、テレビコマーシャル、SNS、インターネット広告等による周知を行うとともに、各都道府県等に対して、「マスクの着用に関するリーフレットについて(更なる周知のお願い)」(令和四年十月十四日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等において、「本人の意に反してマスクの着脱を無理強いすることにならないよう」配慮した適切な情報発信を依頼してきたところであり、引き続き、テレビコマーシャル等も活用しながら、必要な取組を進めてまいりたい。
神谷宗幣(参政党)
屋内で人と人との間隔が二メートル以下ならマスク推奨という目安があるが、その根拠は何か。特に、年齢や健康状態によって個人の免疫力には大きな差異があるが、この二メートルの目安は、そうした免疫力の差異を考慮したものか。二メートルという目安であれば、学校や集会所での脱マスクはほぼ不可能となるし、成長途上の児童生徒の呼吸や体熱発散の妨げになることが明らかなマスク着用のリスクがいつまでも回避できない。施設内などのマスク着用の判断は年齢層や健康状態を考慮して弾力的にしていくべきではないか。
政府
お尋ねの「屋内で人と人との間隔が二メートル以下ならマスク推奨という目安」については、御指摘の「免疫力の差異」を考慮したものではなく、令和四年三月二十八日に国立感染症研究所が世界保健機関及び米国疾病予防管理センターの知見を踏まえて作成し、公表した「新型コロナウイルス(SARS―CoV―二)の感染経路について」において、「感染者との距離が近いほど(概ね一―二メートル以内)感染する可能性が高く、距離が遠いほど(概ね一―二メートル以上)感染する可能性は低くなる」とされていること等を踏まえ、基本的対処方針に記載されているとおり、「屋内において、他者と身体的距離(二メートル以上を目安)がとれない場合、他者と距離がとれるが会話を行う場合、屋外において他者と距離がとれず会話を行う場合は、マスクの着用を推奨する」としているものである。「マスク着用の判断は年齢層や健康状態を考慮して弾力的にしていくべきではないか」とのお尋ねについては、政府としては、マスクの着用については、新型コロナウイルス感染症の基本的な感染対策として、場面に応じた適切なマスクの着脱が重要であると考えており、屋内においては、他者との距離が確保できており、会話がほとんどない場合は、マスクの着用は必要ないこと等を国民に対して、引き続き、周知してまいりたい。その上で、学校におけるマスクの着用については、文部科学省において、都道府県教育委員会等に対し、「マスクの着用に関するリーフレットについて(更なる周知のお願い)」(令和四年十月十九日付け文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡)等により、屋内外において、「十分な身体的距離が確保できる場合には着用の必要がないこと」、「体育の授業や運動部活動の活動中・・・には、感染対策上の工夫や配慮を行いながら、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること」等とした上で、「学校現場において、活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるよう」依頼しているところである。また、子どものマスクの着用については、厚生労働省のホームページのQ&Aに記載されているとおり、屋内外において、「乳幼児(小学校に上がる前の年齢)のマスクの着用には注意が必要であり、特に二歳未満では推奨され」ないこと、「二歳以上の就学前の子どもについても、個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要があることから、他者との身体的距離にかかわらず、マスク着用を一律には求めて」いないこと、「本人の体調がすぐれず持続的なマスクの着用が難しい場合は、無理に着用する必要はな」いこと等について、厚生労働省のホームページ、リーフレット等により周知を行っているところである。